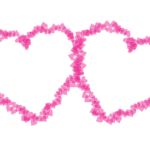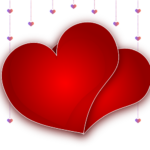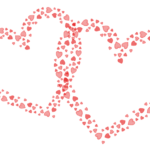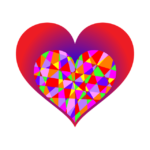彼女はT子、彼はK君。
ふたりは同じ高校の1学年違いで、15歳と16歳の出会いだった。
T子新入学の春が終わる前に、お互い好きになっていた。
それから2年後、K君が一足先に卒業した。
大学浪人生となったK君は、前ほどT子に構わなくなった。
ひとりでいるのがつらかったT子は、K君以外の男の子ともずいぶん仲良くした。
K君もまた、T子以外の女の子と仲良くすることがよくあった。
そんなふうにして45年の月日があった。
K君が61歳で病死するまで、ふたりの仲は途切れ途切れに続いた。
その45年のうち、最後の12年間に、ふたりはメールのやりとりをした。
それが膨大な交信記録となって、T子の手元に残っている。
交信のはじまりは2004年。
T子の名刺にメルアドが記載されており、それを捨てずに持っていたK君がアクセスしたのだった。
ふたりが言葉を交わすのは、数年ぶりだった。
そして4年がたち、今は2008年──。
【2008 January】
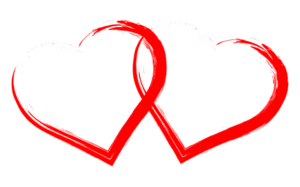
●K君──あけましておめでとう。
タイの仕事は終わりました。
2月9日公開の『L』という作品になります。
失敗作です。
「下手なシナリオからいい映画は出来ない」ということですから、このことは撮る前からわかっていました。
『デスノート』大ヒットの成功報酬代わりに貰った仕事でした。
80億円売り上げた映画のプロデユーサーなのだが、実入りはない。
「ローリングストーンしてください」で終わったわけだ。
で、いまそのローリングが停まっている。
☆☆
タイ経験はよかった。
タイという地理的視点からモノごとを見る。
頭の上に中国が横たわっていた。
バンコクのホテルの前の道をとぼとぼと東に歩けば、カンボジアに行ける。
ロケした村の山の峰を越えればそこはビルマだった。
☆☆
帰国後『(仮)漢字で感じる北京五輪』という企画を考えていた。
ノートにはまとめた。
日本人だから判る漢字(中国語)。
ということは中国人も漢字(日本語)がわかるということだ。
中国人の考える「中国」とは、「漢字」で意思疎通が可能な所である。
朝鮮半島、ベトナムでは漢字を廃止したので、日本が中国のほか唯一の「漢字」国である。
そのことは、北京五輪観戦にしろ「上海万博詣で」にしろ、日本人にとって「理解」のアドヴァンテージを与えるし、また独特のニュアンス「面白み」を味わえることになる。
全てが「漢字」で書き表される。
例外は「[上に下]拉OK]カラオケと「阿Q世伝」を知るのみ
☆☆
問題:中国語で「薩摩」とはどこの国?
答:「サモア」
問題:「足球」はサッカー、「手球」はどんな競技?
答:「ハンドボール」
問題:「南天群星」って何のこと?
答:「サザンオールスターズ」
問題:「布拉徳皮徳」って誰?
答:「ブラッドピット」
問題:「羅森」、「優衣庫」は?
答:「ローソン」「ユニクロ」
問題:「超人」はスーパーマン、では「面包超人」は?
答:「アンパンマン」
問題:「唐老鴨」「米老鼠」は?
答:「ドナルドダック」「ミッキーマウス」
問題:「愛馬仕」「紀梵希」「古姿」?
答:「エルメス」「ジヴァンシー」「グッチ」
問題:「普拉達」「華倫天奴」?
答:「プラダ」「バレンテイノ」
問題:「植村秀」は?「万字醤油」は?
答:「シュウウエムラ」「キッコーマン」
問題:「麦当労」はマクドナルド、「星巴克珈琲」は?
答:「スターバックス」
などなど…。
良妻賢母は中国では「賢妻良母」となる。
「便利店」はコンビニ。
「超市」はスーバーマーケット。
「百貨店中心」は「デパートメントセンター」。
「建材超市」でホームセンターとなる。
「保齢球」とはボーリング。
「馬球」でブランド名ポロ。
「黒球」は八百長のこと。
☆☆
国名地名人名企業名商品名ブランド名などを網羅。
勘のいい人は、これだけで中国語(標準語)の「音」と、使用文字の傾向がわかる。
即ち中国語がわかる。
中国語表記のほうが「原音」に近いものがある。
☆☆
タイでは、中国語で書かれたタイの地図を買った。
タイ語は読めないし、日本語英語では「意味」がわからない。
☆☆
しかし、これでは単に「中国語の外国語表記」というカタログになってしまう。
昨年末福田首相は中国の大学で『温故創新』と揮毫したが、これはブッシュにもプーチンにも真似のできないことだ。
同時に理解できるのも中国人と日本人しかいない。
☆☆
『デスノート』は中国では『死亡筆記』或いは『死亡筆記本』と訳された。
ところが、「死亡筆記ごっこ」が子供たちの間に流行し、発禁回収となった。
文字というものが重たい言霊(文字霊)の国だということを実感させる現象であった。
が、因みに『デスノート』集英社は中国の出版社とは契約していないという。
発禁回収は、海賊版であった。
☆☆
中国の五輪参加史を辿る。
中国現代史そのままに、『二つの中国』問題が浮かび上がる。
台湾は『チャイニーズタイペイ』として参加するのだが、この中国語訳(漢字訳)を巡って大論争となった。
すなわち『中国台北』と訳すか『中華台北』と訳すかである。
この論争にはIOCブランデージ会長もさじを投げた。
この論争の意味を理解していたのは、ほかに日本の委員しかいない。
☆☆
これも「漢字」を巡る話。
1972年名古屋で国際卓球競技大会が開かれた。
ここで世に言う『ピンポン外交』が繰り広げられ、米中の接近が図られ、国交回復に繋がっていく。
それによって、日本も中国と国交樹立、台湾と断交することになる。
テレサテンは、この頃「ニセパスポート事件(ということになっている)」によって日本に入国できず国外退去処分になった。
☆☆
やがて『北京の春』を迎え、文革を終えた。
中国人はこの頃千昌夫の『北国の春』を盛んに愛唱した。
これはあきらかに『北京の春』という意趣を隠喩していた。
☆☆
テレサテン麗君の『何日君再来』が大陸でヒットする。
台湾国民党から大陸に統一を呼びかける歌であるとして、北京政府は発禁放送禁止とした。
この歌、実は戦後台湾でも放送禁止となっている。
それはこの時と逆の意味で、大陸から「帰ってこいよ」と呼びかけていると解釈されたのだ。
☆☆
さらに戦中日本でも抗日歌として排斥された。
「君」の音と「軍」の音が同じであるため。
蒋介石軍に「戻って来い」と呼びかけていると解釈したのだ。
☆☆
大陸の人々は禁止されてもテレサの歌声を支持した。
『昼は老が、夜は小が支配している』言われたのはこの頃である。
即ち昼は小平が、夜は麗君テレサテンという。
テレサに『香港』という名曲がある。
香港返還を見ることなく、ふたりはそれぞれ逝った。
☆☆
因みに「ホンコン」と発音するのは広東語であり、北京語(標準語)では「シャンガン」という。
☆☆
北京五輪公式記録映画の監督は張芸謀ではなく、テレビ局の女性デイレクターとなった。
レニ・リーフェンシュタールのベルリン以来。
北京五輪は「大ピンポン外交」の舞台になる。
いわんや、ベルリンを凌ぐ空前のプロパガンダ五輪となる。
そのプロパガンダ戦略の解説など織り込みながら、「北京の歩き方」にもなるよう配慮する。
☆☆
『靖国』
字義解釈すれば「青い国が立つ」。
「清国復興」になるではないか。
発音は『靖国』も「清国」も「チングォ」。
折角辛亥革命で倒した異民族王朝大清帝国の復活では、中国は納得できないはずだ。
実はこれを言いたい。
どこか出版に乗ってくれるとこないかな。
あなたと共著でもいいよ。ゴーストでなければ。
○○書房には、一昨年の段階で「うちはやりません」と言われたけれど。
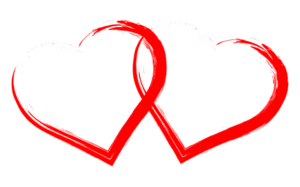
●T子──新年おめでとうございます。
出版企画、がんばりましたね。
ノンフィクションが苦手なわたしには真似のできない発想です。
「企画の○○○○さん」を通じて各社に回してもらうといいよ。
何百人もの編集者が見ているそうだから、名乗りを挙げるところがあるかもしれない。
企画書の書き方、その後のフォロー、印税の配分など、詳細を確かめてからにしなさいね。
ウワサによると、フォローがてんでなってないくせに、商談成立すると印税だけはバッチリ○%もっていく、とのことです。
それでも、企画を売り込みたい個人のための合理的システムと言えますから、利用価値はあるでしょう。
☆☆
純然たる北京五輪ガイドブックではなく、変わりゆく中国の首都観光案内でもなく、「漢字文化都市の日中サブカルチャー本」という位置づけでいいのですよね。
いま一番知りたい都市・Peking/Beijing(?)を一足先に模擬体験、五輪開催を契機に街はこんなことになってるよ、資本主義世界をすっぽり飲み込む当て字文化が面白いよ、日本人だから解読できるディープな裏事情がいっぱいあるよ、という感じかな。
☆☆
写真も仰山入るのかな。
だとしたら、近々に取材に飛ばなくてはね。
☆☆
そこんとこ、もっとはっきり打ち出して、一瞬でコンセプトが伝わる企画書(特に目次が大事かな)に仕上げてください。
そうすれば、きっとうまくいく。
…………………………
●K君──意見ありがとう。
あてのないものを、ひとりでやってると、飽きたりダレタリする。
人の意見は聞いてみるもんだ。
しかし、「書ける」のと「書く」のはちがう。
頭の中はまとまっていても、書く労働意欲は、対価が見えないと「いかない」。
…………………………
●T子──企画書の件、急を要するわけだよね。
ざっと目を通しただけだし、わたしも理解が浅いとは思うけど、いくつか感じたままを述べさせてもらいます。
☆☆
読者対象を明確にイメージして、その人々に語りかけるような企画書にしたほうがいいと思う。
〜は実は〜だった、
かつて〜は〜しちゃった、
だからあなたも〜しちゃおう、
〜は〜で〜になっちゃうぞ、
〜は〜だから〜だ、とか。
わあ面白そう、読んでみたいと思わせる見出しをたくさんつくってみて。
☆☆
今のまま、1955年生まれのK君っぽいのもいいけれど、評論集みたいになる気配がある。
そうではなくて、サブカルチャー本という個性を強調して「売り」をはっきりさせると、編集者の食いつきがよくなるでしょう。
【2008 May】
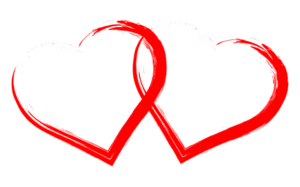
●T子──<童話の原型は親殺しの物語>
昨晩はお電話をありがとう。
考えてみると私、去年の今頃は「絵本をつくりたい」という気分になって、2本ばかり書いてみたのだった。
肝心の絵が用意できず、どこにもプレゼンしていないけど。
かなり恥ずかしいが、思い切って送信してみる。
読んでみてくだされ。