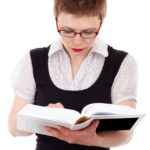日本語にはちょっと変わった特性があります。
(例)お腹すいていませんか。
(例)食事は済ませてきました。
などは、「誰が」という「主語」がなくても、それが誰のことなのか、または誰がしたことなのか、なんとなく判別がついてしまうのです。
私たちは、「述語」を聞いて(または読んで)、その「主語」が誰のことを指しているか、推察することができます。
(あなたは)「お腹がすいている?」、(私は)「食事を済ませた」ということですよね。
しかし、たとえば「お腹がすいている」「食事は済ませた」というような「述語」の部分が欠落していると、その文は意味をなさず、何が言いたいのかさっぱり分かりません。
そのため、述語が省略されることは滅多にないのです。

では、たとえば──
という文における2つの述語「言わない」と「分からない」の主語は、同じ一人の人物を指しているのでしょうか?
答えは、「同一人物ではない」ですよね。
「言わない」の主語と「分からない」の主語は別人だということが読み取れます。
というように、語られなかった主語が2つ、隠れています。
それが誰と誰のことを指すのか、わざわざ語らなくても通じると思われる場合は、主語を省略してしまうわけです。
その結果、主語が1つもない1つの文に述語が2つある、という状態になります。
その2つの述語にはそれぞれ「隠れ主語」がある、と意識してものを言ったり書いたりしているぶんには良いのですが、あまり意識せずに文を作っていることって意外と多いようです。
そうすると、私のように神経質な人間は、「隠れ主語があることは分かっているけど、主語と述語のつながり方が微妙にねじれているようで気持ち悪い」と感じてしまうことが時々あります。
では、どうだったら良いかというと──
「言わないと分からない」ではなく、

「貸した金、返せ」ではなく、

「私は誰も倒せない」ではなく、

というように、主語(および隠れ主語)が1つだけの文にすれば良いのではないかと思います。

そして、皆様もうお気づきかと思いますが、主語および隠れ主語が2つある場合は、主語が変わる箇所で「、」を打つようにすると良いのですね。
「言わないと分からない」という書き方をせず、「言わないと、分からない」というように、「言わない人」を主語とする文と、「分からない人」を主語にする文の境目に「、」を打っておけば、隠れ主語は1つだけでなく2つあるのだということが伝わりやすくなるのではないでしょうか。

余談ですが、次のような文も、私は気持ち悪いと感じてしまいます。
話し言葉としてはこれでも良いのでしょうが、書き言葉としては、つまり文章として書く場合には、もう少し、配慮が必要だと思います。

「誉められて喜ばない人はいない」ではなく、
というように「も」をつけ加えてほしい。または、
というように丁寧に書いてほしい、と思うのは私だけでしょうか?