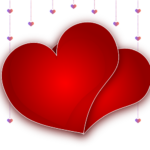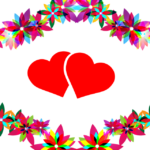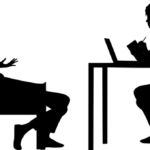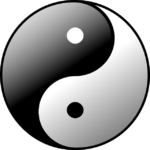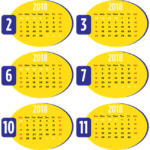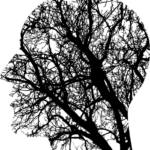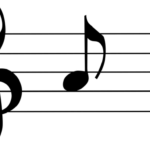【2011 September】
●K君──黄昏の9・11(ナインイレブン)
日中の残暑はまだ厳しい。今日も暑かった。あの日も絶望の最中でのたうちまわり、そして泥酔し女のベッドで寝返りを繰り返す。つけっぱなしのテレビが映しだすあの映像を酔眼で捉えた。しかし、再び毛布を引き上げ寝返る。今の映像は何だ。飛行機が超高層ビルに突っ込んだ。ハリウッド自慢のSFX。絶望はアンブリンどものCG映像としか認識させない。
ねえ、女が肩口を揺り動かす。振り向けば、女はテレビの画面を見つめている。別の飛行機がNYの貿易センターツインビルに衝突する。衝突ではない体当たりだ。カミカゼアタック。自爆テロ。激突、炎上、爆発。泥酔からそしてプライベートな絶望から覚醒した。スピルバーグの新作ではなかった。
やがて高熱に焼かれた鉄とコンクリートの巨大なかたまりは溶けだし、破片となって空を舞い地上に降った。そして摩天楼がゆっくりと崩れ落ちる、そのさまを見た。
十年が過ぎた。
幾つかのささやかなエピソードを残して、女は去っていった。中学受験の娘のいる家庭に戻ったが、その娘も大学四年生になった。
しかし、プライベートな絶望は相変わらず続いている。数年で還暦という年齢ならば、たいした希望があるわけではない。フリーランスゆえの日々のたつきがままならない。9・11で世界は劇的に変わった。しかしプライベートな絶望感は十年一日。この国の空虚感閉塞感また同じだろう。
泥酔していた。飲み続けていた。齢を重ねれば新たな状況も生じる。老母の介護認定を申請したのは、五十六回目の誕生日の日。老母介護と称して家庭放棄、実家に逃避した。
十年目の夜が明けた。もはや家庭に戻る場所はないだろう。娘の花嫁姿を見ることもないに違いない。老い衰え呆けていく老母の最期を待つ。
あの日も暑かった。しかし、眼前の半島最高峰の山の木々も、微かにアースカラーの色素を纏い始めたようだ。
(2011・9・12)
返信不要

●K君──65冊目の日記になった。
「仕事の邪魔にならない」と言ってくれて嬉しい。
誰かに語っていないと、精神バランスが保てない。
心痛。
落ち着かないと、書けない。
落ち着くと、書かない。
落ち着かないと、不安で飲んでしまう。
落ち着くと、安心して飲む。
☆☆
『スクランブル』も『どぶ板』だ。
モラトリアムを支えるアジールだ。
日常と非日常という境界ではなく、多分、聖と俗。
俗に寄りかかりながら、実は「聖性」を描きたいのだと思う。
『東電OL』にも、聖性を見るが。
焼売弁当は値段を書いて。
魂は細部に宿る。
そして森は、魂鎮める。
…………………………
●T子──野坂の本、古本ですが、Amazonから送る。
前にもらった名刺に横須賀の住所を書いてもらったのだった。
送ります。
…………………………
●K君──近年では『文壇』がおもしろかった。
彼は、永井荷風を志向した。
ダンタョウテイニチジョウ。
しかし、『アメリカひじき』の焼け跡闇市派で、いい。
「横須賀どぶ板派」で、いいよな。
二人でやろう。
「ミッドウェー世代」なんて呼ばれ方も悪くない。
ベストは「MOJO派」だけど。
☆☆
三島は『豊穣の海』読みなおしたい。
今なら素直に読めるだろう。
昔は背伸びしていた。
☆☆
内藤ミカは、やめたほうがいいよ。
☆☆
観念と想像力でいくなら、「失意のバカンスで訪れたアメリカに近い場所」。
あるいは外れの田舎町。
そこで昔の横須賀を、どぶ板を知っている落ちぶれた白人の男に出会う。
アンソニーパーキンスに似た男。
その出会いの数日間。
回想は、どぶ板の外人バーにも中華街の外れの妖しいホテルにも飛べる。

●K君──また気分を害した様子は想像に固くないが、如何か。
…………………………
●T子──
>気分を害した様子は想像に固くないが、如何か。
↑固い、ではなく、難い。
☆☆
別に気分害していないし、↑の文体笑えてよろしい。
☆☆
野坂氏の意外な側面が窺える本。
いずれ評伝書くときの参考になるはず。
…………………………
●K君──度しがたい。
携帯、変換してくれない。
恥ずかしいだろ。
あれが固い。あれが難い。
十五夜だよ。
…………………………
●T子──ちょうど今、中国式お月見について書こうとしていたところ。
…………………………
●K君──君に準じて「お月見考」書いていたが、暫し休憩。
戯れ言を。また。
歴史は夜作られる。
愛していようがいまいが、男と女が一晩過ごせば歴史はできる。
合意であろうとレ○プであろうと。
そうでなければ、南米の国はない。
でも南米人は言った。
歴史ができるのは、夜とは限らない。
カソリックだからだ。
返信不要。
「もうあの人は死んだことにしようよ」

●K君──歴史とは、膨大なまぐわいの記録である。
歴史書とは、至高のポル○グラフィである。
歴史書をひもといて、エク○タシーを得られぬは、想像力の欠如である。
変身不要、変装不要。
朝から「馬鹿」である。
イギリス作家ハミルトン・カーは言った。
日本では、国語でポ○ノを扱うのか、と。
…………………………
●T子──書き出しから描写を変えた。
ちょっと長いけど、また送ってもいいかなあ?
すみませんが再読を。
☆☆
午前九時過ぎ、ホテル従業員用の裏口から出て駐車場を突っ切ると、そこは中華街のはずれの北門通りである。街の東西南北を護る四神のうち、北の守護神である亀を象徴する黒門柱が目前に聳えている。玄武門である。これを潜り抜ければ、ヨコハマチャイナからジャパンへと時空が切り替わる。門の向こう側、すぐそこに区役所が見えている。公園とスタジアムの先には市役所がある。
あっち戻るか、と思いつつも足は逆方向を向く。さしあたり、急ぐ用事はないのだ。今日は本業のほうの打合せを進めるつもりでいるが、顧客に連絡をとるのは、いつものとおり午後からで構わない。だからもうしばらくはこのまま、日常とも非日常ともつかぬ曖昧な感覚を味わっていたい。
すでに十六時間、日常を離れている。昨日は夕方四時にホテルに入り、在日韓国人やら出稼ぎ組やらに囲まれて一晩過ごした。言葉も動作も荒々しい女たちに混じってタオルやシーツを腕いっぱいに抱えて運び、慣れない手つきでベッドメイキングをし、客が残していったごみや汚物の後片付けに追われていたのだから、いつもの自分などどこかに吹き飛んでしまった。目先の仕事に応じるだけで手一杯、よけいなことを考えている余裕などなかった。
「二〇三号室が空いたから即お掃除お願い。お客さんがロビーで待ってるの」
控えの間で待機していると、フロントからインターフォンが入る。するとまず真っ先に、在日のキムさんがヨシキタと声を出して腰を上げる。同じく在日のタカギさんはゴミを集めるバケツを手に立ち上がる。出稼ぎ組のソンさん、チョウさん、ゴさんはそれぞれ、新しいシーツとタオル一式、掃除用具を詰めこんだカゴ、石けん・シャンプー・リンス・歯ブラシセット・コンドームといったアメニティグッズのカゴを持つ。出稼ぎの三人は出動のたびに三種の手荷物を交代しているが、どれもそれほど重さは変わらない。つねに一番重いものを持たされるのは新入りである。客室の冷蔵庫に補充するための缶ビール、ワンカップ酒、ジュース、コーラ、オロナミンCがぎっしり詰まったバスケットは無駄に重い。どの客室でどの飲料が消費されたか、フロントに確かめてから出動すればいいものを、そんなややこしいことをするくらいなら、持てるだけ持っていっちまえというのが、ここでのしきたりなのである。
午前二時をまわり、満室になると、我々泊まりの清掃員は顔を洗って夜食のカップラーメンをすすり、立て続けに三本ほど煙草を吸うと、控えの間に隣接する仮眠室へ引き上げる。六畳の和室に六人の女が雑魚寝をする。だが一人につき畳半畳分しか与えられないのは、フロントや昼の部の清掃員も含めた全従業員のロッカーが部屋の半分近くを占めているせいだった。
皆に倣って制服の上着を脱ぎ、誰が使ったかわからない古布団にくるまった。灯りを消すと、すぐに韓国の女たちはいびきをかきはじめた。こちらはいつまでも寝つけずに、こんなところでいったい何をしているのだろうと、情けなくなった。泣くまいと思っても、あとからあとから涙がこぼれた。
それでも朝方には少しうとうとして、六時半の目覚ましで浅い眠りを破られた。出稼ぎの先輩たちに教わりながら布団を三つ折りにたたみ、押し入れの右半分に二列に重ねた。「こっち側はワタシたちの布団デスヨ、あっち側は明日の夜のヒトたちのぶんなのデスヨ」
と在日のタカノさんが解説してくれた。
「部屋、いくつ空いたか」とキムさんがフロントに聞く。
「五個」
「じゃ、やるか?」
「いいよ、急がなくて。今から入ってくる客なんかいやしないよ。今日は平日だもん」
「アイゴー、ウチはまた行列ができてるかと思った」
「昼間の人たちが来る前に、空いてる部屋だけざっと片付けといて」
「そんなら楽だ」
というわけで我々は控えの間でテーブルを囲み、インスタントコーヒーと煙草をやった。これで最初の一夜が明けたのだ、と思うと少し気が楽になった。
昼の部の人たちは、一部屋あたり小一時間ほどもかけて念入りに清掃をするらしい。我々夜の部は汚れ物を処理して備品を補充し、ベッドメイキングだけはきちんとやるけれど、いちいちバスルームの掃除なんかしなかった。風呂に湯がたまっていれば栓を外し、湯が抜けきるまでの間に、使用済みのタオルでバスルーム全体をささっと拭いて乾かし、それでおしまい。便器も特に汚れていなければタオルでざっとぬぐい、「消毒済」と印刷された紙帯をかけて完了。ところが昼の部は、バスもトイレも丁寧に洗剤で磨き上げる。月に一度はカビキラーを施す。じゅうたんに掃除機をかけることも一日おきにやっているとのことである。
「大変ですね」と感想をもらすと、「あのヒトたちは日本人デスから。きれい好きなんデスヨ」とタカギさんは言った。そして、こうも言った。「あのヒトたち、毎日お風呂にはいっているでしょ」
「さ、やろか」とキムさんが言うので、我々六人は再び手荷物を抱えてエレベーターに乗りこんだ。各フロアをまわり、空部屋を探して入る。これも事前にフロントで確かめてから来ればいいものを、キムさんの気が短いせいか、あるいはフロントに指示されることを内心嫌っているせいか、合理的な行動ができないのである。六人のうち二人はベッドのシーツをはがし、一人はタオルを集め、各階ごと廊下の隅に備わる使用済みリネンの麻袋に放りこむ。あとの一人は新しいシーツとタオル一式をベッドの上に置き、アメニティと飲み物の補充をする。残りの二人は、空部屋を探してまわる。朝の仕事はそれだけだった。
九時近くなると、昼の部の人たちが次々やってきた。夜の部と同じで、全部で六人。みな日本のおばさんで、年は五十代から六十代、タカシマヤで買ったのかなと思わせる洒落たセーターなど着ていた。
「アンドーさん、紹介しよう」
とフロントからイシダさんが出てきた。このイシダさんというのも日本人のおばさんで、かつては関内でクラブを経営していたのだと、面接のときに本人がそう言っていた。
「ゆうべから一人新しく入ったから、おぼえといて」
「あらなに、新しく入ったの? 日本人?」
「日本の人だよね」
「あんた、名前アンドーさんっていうの」
「若いのに、まあ」
「あんた、もったいないよ、こんなとこにいちゃ」
おばさんたちは口々に言った。このときもなぜか、涙がこぼれそうになった。
日勤組の到着と入れ替わりに、我々夜勤組は制服から私服に着替え、化粧を整えて、タイムカードに退勤時刻を刻印したのだった。
陽はとうに海を遠く離れ、南門の真上あたりの中空に浮いている。冬場の微弱な陽光が中華街大通りを照らし、白い一筋の道をつけている。これを辿っていって前田橋を渡れば元町に出るから、そこでゆっくりお茶を飲みながら時間をつぶせばいい。午後の打ち合わせに備えて、もう一度資料に目を通しておきたい。
だが待てよ。元町でお茶もいいけれど、その前に何か食べなくては。肉体労働のあとだから、滋養のある食事をしたい。この時間に開いているのは、聘珍樓の飲茶くらいしか思いつかない。あそこなら朝八時にはもう蒸籠から湯気があがっているし、お粥の用意もできている。ただ、値段に少々問題がある。鉄観音茶とともに小籠包、春巻き、牛肉球と数皿やれば、ラブホテル清掃員四時間分の時給が消える。
今はそんな贅沢が許される身ではない。なにしろ千二百万の借金があり、本業のデザインの仕事だけでは返していくことはむずかしいのだ。昨日のように、アルバイト先のホテルにタクシーで乗りつけるなんてことも二度としてはいけない。夕飯はお弁当持参で、とイシダさんから言われていたのだが、崎陽軒のシウマイ弁当を買っていくのも愚かであった。韓国の先輩がたは、自分で炊いた飯、手製のキムチ、ナムル、そのほか数種のおかずを持ち寄り、分け合って食べていた。いくらか日本語を喋れる出稼ぎのソンさんが、コレイクラ、とシウマイ弁当を指差して聞くので値段を教えると、目をむいて驚かれた。こちらとしては、それほど高いものじゃなかろうという気で、日頃ちょくちょく利用している。だが、初出勤から夕飯までのわずか三時間にいくらか気が変わっていた。ホテルまでのタクシー代、シウマイ弁当も、我々がこのホテルで働く一時間分の給金にほぼ相当するのだ。ここでの一時間の長さを思うと、とてもじゃないがもう気軽に手を出せなくなる。体を使って得るもの、あるいは汚物に親しむことで失うものと引き替えに贅沢をしたってはじまらない。
金を稼ぐよりも遣うほうが盛んで借金がかさみ、ついに一千万を越えたのである。それでも半年前なら、借金の元である男と別れて仕事に精を出しさえすれば、返して返せない額ではなかった。そう見込みをつけて男を追い出し、仕事に専念しようとしていた矢先に、受注量が激減したのだった。つねに何かしらオファーをくれた広告代理店からして、仕事が半分に減ってしまったと青ざめていた。こちらと直接取引のある元町のブティックやレストランでも、売上げが低迷したまま持ち直さないと嘆いていた。新商品開発のプロジェクトチームに外部スタッフとして加わってくれ、と声をかけられることなどまったくなくなった。新商品が生まれなければ、ロゴマークやパッケージデザインは必要とされない。販売促進用のパンフレットもDMもお呼びじゃない。
フリーのデザイナーとして独立開業してからこの十数年、ずっと右肩上がりできただけに、初めて経験する不況はこたえた。こちらは仕事に応じて自由に契約するフリーランサーの立場であり、企業、団体、組織のいずれにも
…………………………
●K君──読んだ
まあ、携帯で読むもんじゃない。
200枚中編までいけるか?
自分の経験は「素材」だと思うけど、それを私小説で処理するのか、中間小説にするのか。
大いなるフィクションは許されているはずだ。
借金抱えた広告屋が、初日から涙をこぼしたって、言われても。
ならば、中華街の描写から「悲しい色やねん」。
でも、実は「そこも、解放区であって、救われた」ってお話しになるわけでしょう。
短編で処理するならば、韓国からきたおばちゃんが、自分のみすぎよすぎを語る。
故郷の家族のこと。
間に仕事して、主人公の人生の事情を探る。
一晩のお話し。
キムチと焼売を食べながら。
いびきをかかせたら、「自分もあんなふうにいびきをかきたい」と受けなければ。
在日と半島から来た人の書き分けも意味をなしてない。
Takashimayaは前の日の引き継ぎ。
ルポルタージュなら、「テーマ」をはっきりと。
主人公の状況は、「テーマ」を受け止める属性である。
…………………………
●T子──いろいろ考えなければいけません。
横浜のロマンティシズムと開放感に救われた、横須賀から解放された、というのは30年前のこと。
この小説に書くのは20年前の出来事だけれど、フリーランサーをめぐる状況は今も当時と全く変わっていない。
だからこれは現在進行中の話でもあり。
テーマは自由への讃歌が第一で、第二に仕事への愛。
それとは別格に、「街の猥雑さが生きる力を与える」ということ。
これはドブ板と共通すること。
私の構想は甘いですか?
たしかに、このままでは駄目なのでしょう。
考える。
…………………………
●K君──
一応返信する
表現したいことは、知っているし、わかっている。
それが文学上で展開させるのならば、簡単ではない。
勿論、ゴーストライターの延長線上にあるならいいよ。
ライターと文学は、別だよ。
もんぞう修行はそれとして。
それが邪魔してる。
☆☆
高橋治の横に著作を並べる娘、もうおばちゃんの高名なシナリオライター「作家」が、人を介して連絡をよこした。「オーラをください」と。
「もう、ねえよ。そんなもん」
彼女のスランプは見てとれていたが、トレンディドラマで売れたはいいが、使い捨て。
彼女もその作法から抜け出ることができない。
☆☆
女流の皆さん、結末なしに、ラスト1行逆算なしに、つらつらだが。
勿論変わってもいいが、ラストの想定はあっていい。
向田邦子は、シナリオも小説も「ラスト」があった。
その意味では、男流っぽい。
毛嫌いせずに。
薦めます。
☆☆
「構成」を作ったら、どう?
こういう作業はしてきたのだから。
☆☆
さあ、婆さんの晩飯だ。
炊き込みご飯でもつくるか。
…………………………
●T子──1つだけ手短に教えていただけますか。
第1稿よりも第2稿はレベルが下がった、という評価?
…………………………
●K君──第1稿でも2稿でもない。
かわらない。
パソコン使うと、簡単に1稿2稿と、さも大直ししたようにいう。
大勢がかわらなければ、同番。
☆☆
初めて受けとる台本が十数稿。
全然成立してねぇてことじゃん。
初稿までに、どれほど推敲し、苦しむのか。
そんなに簡単になおせない。
映画のシナリオづくりでは、ここで血みどろの戦いとなる。
1行直すのに1月。
直らず、葬ったもの多々あり。
人に厳しかったのに、自分にだけ安易を良し、とはならない。
だから、この様か。
…………………………
●T子──なによ、そんな言い方して。
もうやだ。
ひとりで考える。
…………………………
●K君──基本的には、そういうもんだ。
阿呆のアフォリズムを、阿波踊りという。
…………………………
●T子──
>人に厳しかったのに、自分にだけ安易を良し、とはならない。だから、この様か。
↑この様かって、自分のことなの?
…………………………
●K君──
>この様かって、自分のことなの?
↑そう。
因みに、ハミルトン・カーなる英国作家は実在しません。
…………………………
●T子──これが最後だから
読んでもらうのは、これを最後にするから送らせて。
冒頭は決まった。
ラストはカタストロフにする。
中国人の男とも別れて借金ますます増えて、万事破局で茫然自失。
現象面ではそういうことだけど、心中ひそかに幻視の街「YHM迷路」が浮かび上がり、性懲りもなく再生の兆し、という結末です。
☆☆
昭和三十年代の覚えには、つねに陶酔と戦慄がつきまとう。ようやく遠出もできるほど足がしっかりしてきた幼な児の手を引き、京浜急行日ノ出町駅の薄暗い階段を降りる母の姿が記憶の底に見え隠れする。駅の裏手に、婦人服縫製の内職をする女が住んでいて、母は横須賀に嫁いだのちも懇意にし、裁縫の腕などいくらもないはずなのに、週に一度、お針子の一人として使ってもらっていたのである。
駅前の角を曲がった裏道にはあばら屋が建ち並び、だが人の気配もなく閑として、幼心にも荒涼というものの手触りを知らしめた。母は無言で歩きつづけたが、機嫌が悪いというわけではなかった。橫浜に還ってきたことが嬉しくてならないのである。いつか母が晴れやかに笑いながら、この荒んだ裏道に子を置き去りにするのではないかと、陰鬱な不安が胸にたちこめた。突然泣き出すと、母はびっくりしてその場にしゃがみ、蜂にでも刺されたのではないかと身体のあちこちを調べた。なんともない、と母は言い、仕立屋の玄関を威勢よく開けた。
帰りは駅前の雑踏の中で母が父とおちあい、このまま三人で電車に乗り横須賀の家に戻るのかと思えば、再び駅を離れて川沿いの洋酒バーに入り、苦いカクテルを何杯となく飲むのだった。幼な児は待ちくたびれて寝てしまい、父に抱かれて電車に揺られた。時折ふと目を覚まして母のほうに手をやると、今度は母が抱いてくれた。幼な児は甘い陶酔にひたって眠りをむさぼった。だがその心の片隅で、わけもなく母を危険な女とみなし、恐れおののいているのだった。
現実よりも虚構が強い、と知ったのは、横須賀は安浦のピカデリーという劇場で映画を観せられたことによる。雨の日曜日、父と母は娘にも小さな傘を持たせ、安浦まで坂を下っていった。むろん晴れの日もあった。日曜ごとに観つづけた映画の中に、母が愛してやまない橫浜の街があった。スクリーンを見つめる母の横顔は女優のようであった。橫浜が映し出されると、母はそれだけで自分も偉くなったような気がしていたのだ。橫浜に住めば、まるで映画の中に生きているような気分になれると、母にそっと打ち明けられたような記憶もある。
母にとって、故郷の橫浜に対する思いは骨肉の情であった。横須賀を棄てて橫浜に舞い戻ることばかり考えていた。その願いが叶えられたのは、娘が独り立ちしてすぐのことだった。娘が東京で貧乏住まいをしている間に、父母は橫浜に家を買って移り住んだ。娘のための部屋は用意されていなかった。棄てられたのだ、いつかこうなると思っていた、というのは年に似合わぬ拗ね言、理不尽な言いがかりとわかってはいても、一度芽生えた不安と恐怖、失望と怒りはいつまでもしつこく頭の芯にこびりついていた。
だがやがては心の風向きも変わる。娘は両親の住む橫浜にやってきて、自分もここで暮らすと宣言した。その当時の橫浜は明るく開放的で、なおかつ路地裏に昔の面影を色濃く残していた。豊かでありながら貧しい街、貧しくとも豊かな街。ここはリアリストの住む街じゃない、現実よりも虚構に生きるロマンティックな人々のための街である。母が想う橫浜と、娘の頭の中の橫浜が合致した。日ノ出町からはじまって野毛、福富町、伊勢佐木町、そして関内は馬車道、山下町、中華街、さらに元町、山手、根岸台、本牧と、日々の生活に橫浜がなだれこんできた。街のどこにいても港を感じることができた。横須賀時代から身をむしばみつづけた袋小路の閉塞感が消え失せた。吹きだまりに追いやられているような疎外感からも解放された。
すると次第に運が上向いていった。仕事にも恵まれ、順風満帆であった。暮らし向きは楽になった。ところがあるとき突如として、またもや風向きが変わった。このたびは、景気の風向きがまわれ右をしたのである。
午前九時過ぎ、ホテル従業員用の裏口から出て駐車場を突っ切ると、そこは中華街のはずれの……(続きはまたの機会に)
…………………………
(T子記す)
Kから返信がないのは、相変わらずこれじゃダメだと踏んだからなのか?
おもしろくねえよ、ピンとこないよ、全然成立してねぇ、そう簡単に直せるもんじゃない、もっと苦しめ、と無言のうちに伝えているわけだ。
彼、つきあいがいいほうじゃないからなあ。
それはわかっていたのだけれど。
今までのように、毎日何度もメールをちょうだい。
あなたを感じていたい。
また恋人になれたと喜んでいたのに、あいつはすぐに気が変わってどっか行っちゃう。
茅ヶ崎で会った8月26日、いやその前の8月初頭から9月12日までは幸せだったなあ。
特にデートのあとはメール攻勢が続いたので、あいつもついに私に惚れ直して、とうとう狂ってくれたのかと思うほどだった。
小説のために『ヨコハマ・ウォーキング』再読。
大桟橋からナホトカ航路はまだあるのだろうか。
ナホトカまで2泊3日、わりと低価格。
Kの好きな船旅に出たい。