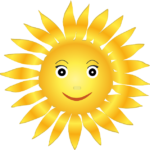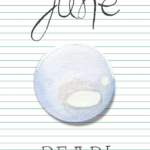日本の年間雨量は、世界平均の約2倍だそうです。
日本列島が、世界有数の多雨地帯(アジアモンスーン地帯)に位置しているためですね。
同じアジアモンスーン地帯でも、インドや東南アジア諸国では雨季と乾季がはっきり分かれています。
それに対し、ここ日本では1年を通じて雨が降ります。
そこで、春雨(はるさめ)、五月雨(さみだれ)、夕立(ゆうだち)、秋霖(しゅうりん)、時雨(しぐれ)など、季節ごとにさまざまな雨の呼称が生まれたのでしょう。
日本の雨について、そして梅雨どきの暮らしについて、お話ししてみたくなりました。
●四季を通じて最も雨が降る時期はいつ?

梅雨時よりも9月・10月のほうが降水量が多いというのは、ちょっと意外ですが、
と気象庁広報誌に記載されています。
↑つまり、秋の長雨、ということですね。
ただし、九州の福岡に焦点をあてると、月降水量が最も多いのは7月で、2番目は6月だそうです。
↑これはやはり、日本列島のうちでも南方へいくほど梅雨時の降水量が多いということでしょう。
●梅雨入りの目安は6月10日
5月中旬以降になると、北方の冷たいオホーツク海高気圧と、南方の暖かい小笠原高気圧とが、日本付近で衝突し、停滞前線を形づくります。
このため、早い年なら5月中旬から沖縄が、続いて6月上旬には九州が梅雨に入ります。
以後、日をおうごとに雨域は北上し、北海道と東北の一部を除く日本全域が、

その年の気圧配置により、また、日本のどの地域に住んでいるかにより、梅雨入りの日は微妙に異なりますが、
6月10日というのは、立春から135日目にあたります。
しかし実際にこの日から梅雨期に入るとは限らず、全国的に、入梅の日は毎年変わります。
5月下旬から梅雨が始まる年もあれば、遅い年は6月末になることもあるのです。
全国的に、雨の日が少ない「からつゆ」の年になることもあります。
「からつゆ」の年は雨量が足りないために作物が生育不良となったり、また、夏に水不足になれば節水を必要とされたりと、生活全般に影響が及びます。
こうしてみると、雨降りが続いてうっとうしい梅雨期も、私たちの生活にとって欠かせない大切なものなのですね。
●ジメジメ・イライラ・ダルダルを解消して快適に暮らしたい

梅雨入りしてから明けるまでに約40日かかります。
布団を干せないので気分よく眠れない。
あまりの湿気に室内にカビがはえてしまった。
なんとなく食欲がわかない。
体がだるい。
など、悩まされることは数多くあります。
つい愚痴のひとつも言いたくなりますが、お天気ばかりはどうしようもありません。
イライラして家族に八つ当たり、なんていうのも避けたいものです。
では、どうすれば梅雨時のジメジメ・イライラ・ダルダルを解消して快適に暮らせるのでしょうか。
そのヒントとなるような情報を探ってみたところ、さっそく今日から実行したいナイスな方法がいくつも見つかりました。
ここではまず、6月の入梅期にぜひ試したいことをいくつかご紹介しますので、参考になさっていただければと思います。
●風呂は熱めの湯に短時間浸かってさっぱりと

梅雨どきをいかに快適に過ごすか。
その要となるのは、湿気といかに上手につきあうか、です。
蒸し暑い、汗ばんだ体がベタベタして気持ち悪い。
湿気というのは厄介なもので、冬場は湿気寒ともなりますから、冷えた体を芯から温めるために、あまり熱くないお湯にゆっくりと浸かることが必要となりますが、夏場は熱めの湯にさっと浸かるだけで良いでしょう。
ジメジメ・ベタベタして気分がすぐれない、ああもうイライラする〜そこですかさず、熱めの湯に入って気分すっきり、体もすっきり。
といっても、一日に何度も入浴するわけにはいかないので、さっとシャワーでも浴びると良いですね。
水流も強めにしておくと、皮膚に圧力がかかって良い刺激となり、だるい体もシャキッと生き返ります。
つまり、筋肉疲労を快復するマッサージ効果があるのです。
また、強いシャワーは水滴が割れるときにマイナスに帯電して空気イオンを発生するので、神経の疲れを癒やして快復させる効果もあるそうです。
●布団乾燥機で安眠を

私たちは毎晩寝ている間に、コップ一杯分の汗をかいています。
その汗を吸っているのが、布団です。
ですから当然、1週間も布団を干さずにいると、じっとりと湿ってきます。
毎日のように雨が降り続くこの季節は、布団を干したくても干せません。
汗の量も増えているはずなので、なおさら布団はじっとり湿って重たくなります。
私自身は布団乾燥機を持っていないのですが、友人宅で使わせてもらったことがあります。
いやあ、↑あれは本当に便利なものですね。
掛け布団と敷き布団の間に布団乾燥機のマットをセットし、スイッチオンにすれば、温風がすばやく広がって、布団全体をむらなく乾燥してくれるのです。
マット式ではなく、ノズルを掛け布団と敷き布団の間に差し込むタイプのものもあるようです。
マット式、ノズル式、いずれであっても、効果のほどはほぼ同じとのことで、30分ほど稼働させれば、布団はふかふかになります。
私もこの夏、ぜひ一台購入しようと思っています。
●残ったビールでナメクジ退治

キッチンの流し台の下やお風呂場をナメクジがはっている!!
そんなとき、さあ、あなたはどうします?
ナメクジは、湿気の多い場所を好みます。
観葉植物の鉢の裏側あたりにもいるかもしれませんよ。
↑私も子どもの頃はよくやりました。
でも今は、ナメクジを見かけるたびに塩をかけて殺すというのは、あまり気が進みません。
できれば、見えないところでそっと退治してしまいたいのです。
といっても、私はマンション住まいで、庭もないので、ナメクジに遭遇することは滅多にありません。
滅多にないどころか、ほぼゼロです。
ただ、ゆくゆくは一軒家に住むことになりそうなので、ナメクジ退治の方法も知っておきたいと思うのです。
それならいい方法があるよ、と友人が教えてくれました。
↓
飲み残しのビールを平皿に入れ、ナメクジが出そうなところに置いておくと、
ほんとかな〜と私は半信半疑でしたが、友人は実際にこの方法で効果を上げているというのです。
私も庭のある家に移り住んだら、さっそく試してみます。
●室内のカビ予防

梅雨時は、ちょっと油断をすると、室内の壁といわず天井といわず、思いがけないところにカビがはえていることがあります。
マンションの場合は、お風呂場に窓がないこともあり、ちょっとでも水滴が残っていると、そこからカビが発生します。
いったんカビがはえてしまうと、ごく普通に掃除をしただけでは根絶できません。
表面的にカビを取り除いても、まだ菌糸が残っているため、またはえてくるのです。
ではどんな掃除をすれば良いかというと、お風呂場の場合は、
室内の壁や床、天井などは、熱めの湯に中性洗剤を溶かしたものに雑巾を浸し、それを絞って雑巾がけをすると良いようです。
消毒用のアルコールは、薬局で購入することができます。
アルコール4に対して水1の割合で薄めた液体をスプレーボトルに詰め、噴霧すると良いでしょう。
漂白剤も殺菌作用がありますが、これは残留成分が体に悪影響を及ぼしますし、使うと手が荒れるので、私はもう何十年も買っていません。
日頃から室内の換気を心がけ、こまめに掃除をする、必要に応じて中性洗剤や消毒用アルコールを用いる、ということで対策は十分だと思います。
●梅雨どきの憂鬱を忘れさせる夏料理

梅雨時の憂さをはらうには、この季節だからこそ味わえるものを存分に楽しむことも一つの方法です。
旬の魚は、鮎・イサキ・イボダイ・クロマグロ・アジ・イシモチ・アジ・イワナなど。
旬の野菜は、キュウリ・枝豆・ゴボウ・サクランボ・青梅など。
若鮎の塩焼き、アワビの酒蒸し、なんていうのも、この季節ならではの貴重な風味であるとされています。
ただ、鮎を姿のまま美しく塩焼きにするには、遠火の強火でなくてはなりませんから、家庭で調理するのはちょっとむずかしそうです。
アワビの身を殻から外すのも、プロの料理人ならいざしらず、我々一般の人はあまり経験がないことなので、手にケガをしてしまうかもしれません。
ここはやはり、多少お値段がはっても、お料理屋さんで美味しくいただくのが賢明なようです。
より手近な食材といえば、サクランボが出回るようになりますが、5月下旬から6月末までと時期が短いので、旬を逃さないようにしたいものです。

キュウリをはじめとするウリ科の食物も良いですね。
日本は瓜天国ともいわれ、胡瓜(キュウリ)、西瓜(スイカ)、南瓜(カボチャ)、甜瓜(マクワウリ)、苦瓜(ニガウリ)、糸瓜(ヘチマ)と種類豊富です。
いまやキュウリは年中ありますが、6月から8月にかけての太陽の直射によって育ったキュウリは、ビニールハウスの温室栽培ものとは味も香りも断然違います。

お風呂で汗を流してさっぱりしたあと、キュウリもみ(酢の物)で冷やをキュッと一杯、続いてこれもやはり季節の美味である梅酒を一杯とくれば、日頃の憂さもスキッと晴れ上がってゴキゲンです。
酢の物を食べると体がしゃきっとし、食欲も増します。
お酢は、食物が体内でエネルギーに変わるときの、いわゆる「燃焼」という生理作用を助け、ひいては血液が酸性に傾くことを防ぎ、よって体を活性化する効果があるのです。
疲れたとき、熱があるとき、また妊娠中など、なぜかたまらなく酸っぱいものが食べたくなるのは、こうした理由があるからなのですね。
●まとめ

梅雨入りから梅雨明けまでの期間は、約40日というのが目安です。
その40日間をできるだけ快適に過ごす秘訣は、湿気と上手につきあうことです。
●布団を干せないときは、布団乾燥機を活用しましょう。
●布団乾燥機があれば、洗濯物をすばやく乾かすこともできます。
●ナメクジ退治にはビールを活用。
●室内のカビ予防には、拭き掃除をしたあと、消毒用アルコールを水で薄めてシュッと噴射。
●梅雨時の憂さをはらうには、この季節だからこそ味わえるものを存分に楽しむことも一つの方法。
●旬の魚は、鮎・イサキ・イボダイ・クロマグロ・アジ・イシモチ・アジ・イワナなど。
●旬の野菜は、キュウリ・枝豆・ゴボウ・サクランボ・青梅など。
●お酢で体をシャキッと。
↑ぜひ試してみましょうね。