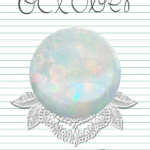2月は1年のうちで最も寒いので、厚着をした上にさらに重ね着をすることから「衣更着」(きさらぎ)と呼ばれるようになったようです。
「きさらぎ」を「如月」と書くのは一種の宛て字かなと思いますが、「如月」は中国伝来の「2月」を指す言葉で、元は「じょげつ」と読んだのだそうです。
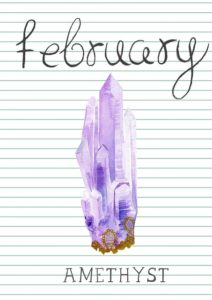
●2月の別名・異称・愛称
陰暦を使っていた当時の2月は、わたしたち現代人が使っている太陽暦でいうところの3月にあたり、春の訪れがそこかしこに感じられる気候だったと思われます。
そこで──
雪消月(ゆきげつき)
梅見月(うめみづき)
初花月(はつはなづき)
とも呼ばれるようになったのですね。風情があります。
仲春(ちゅうしゅん)という呼び方もあります。
これは1月〜3月を春としていた時代の呼称で、「春の真ん中の月」という意味です。
2月は「美しい月」という意味を強調し、
令月(れいげつ)
麗月(れいげつ)
という呼び方もされます。
そのほか──
酣春(かんしゅん)
仲陽(ちゅうよう)
美景(びけい)
令節(れいせつ)
降入(こうにゅう)
華朝(かちょう)
恵風(けいふう)
星鳥(せいちょう)
という別名・異称・愛称がありますが、次第に漢字のむずかしさが増し、意味を読みとりづらいものになっていったようです。