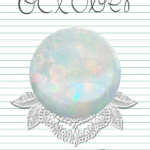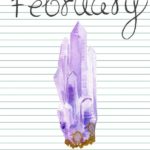日本は雪の多い国です。
沖縄やその周辺の島々は別として、雪が積もったことなど一度もないという地域はまったくといっていいほどないでしょう。
1年の半分を雪にとざされる地域もあり、雪が降り積もれば屋根の雪おろしをしなければなりませんし、道路の除雪をしなければ学校や会社、買い物に行くこともできないので本当に大変でしょう。

住む地域によって、雪とのつきあい方は大きく異なります。
首都圏では、雪が降ってもそう大事には至らないので、私などはとても助かっています。
雪のことをよく知らないまま、
などと、のんきなことを考えたりしています。
でも、「日本庭園の雪見」というだけでは、あまりにイメージが貧困ですね。
雪というものは、もっと奥深いものであるはずです。
北国に暮らしている方々なら、淡雪・粉雪・ぼたん雪など、雪にもいろいろな種類があることを肌身で感じていらっしゃることと思います。
私のように雪に接する機会の少ない者は、まずは言葉を通じて雪の世界に分け入っていくのが良いようです。
●「こんこん」ではなく「こんこ」
「雪やこんこ、アラレやこんこ。降っては降っては、ずんずん積もる」
という歌がありますね。作詞者も作曲者も不詳ですが、広く一般に歌われる文部省唱歌です。
この歌にある「こんこ」を「こんこん」、つまり雪がこんこんと降ることだと思っている人は多いようですが、それは誤解です。
「こんこ」というのは「来ん此」、「ここへ来い来い。もっと降れ」という意味の言葉がなまって変化(転訛)したものだとされています。
「こんこ」がさらに転訛して「こんこん」となってもよさそうですが、雪はこんこんと降るものではなく、涔涔(しんしん)と降り積もるものです。
「こんこん」という語がふさわしいのは、「こんこんと湧き出る泉」「こんこんと眠り続ける」「こんこんと言い聞かせる」などです。
「こんこ」と「こんこん」を取り違えないようにしましょう。
●36種類の「雪」

歳時記にあたってみたところ、雪をあらわす言葉が36種類見つかりました。
ああ日本語っていいなあと思わせる、素敵な響きの語ばかりです。
冬の言葉コレクションとして、ご紹介したいと思います。
・暮雪(ぼせつ)
夕方降る雪、または夕方に見る積雪を指して「暮雪」といいます。
侘び寂びが感じられる、風情のある言葉です。
・淡雪(あわゆき)
ひらひらと降ってくる雪、手にとるとはかなく消えてしまう雪のことを「淡雪」といいます。
淡雪は、暖かくなってから降ることが多いようです。
・斑雪(はだれ)
降り積もった雪が部分的にとけて、地肌が少しのぞいている風景を「はだれ」というんですね。
「白黒まだら」という意味ですが、「はだれ」という表現もあることを、私は初めて知りました。
・雪の果(ゆきのはて)
冬の間よく降った雪も、そろそろこれでおしまいだろうという時季(旧暦2月の頃)のことを「雪の果て」というそうです。
早く「降りじまい」してほしいという願いがこもった言葉ですね。
・秋雪(しゅうせつ)
秋の高山に降る雪は、紅葉とともに豪華な眺めをつくります。
そんな雪のことを「秋雪」といって愛でるのですね。
・初雪(はつゆき)
冬になって初めて降る雪のことです。
「初雪」という言葉の響きは、なんとなく心をなごませ、何かいいことありそうと期待させるものがありますね。
・風花(かざはな)
晴れた空から、はらはらと舞い落ちる雪を「風花」といいます。
せっかくいいお天気なのに雪が降れば寒くなるので困るでしょうが、「風花」という言葉には、華やかな雰囲気を感じます。
・吹雪(ふぶき)
激しい風にあおられて降りしきる雪を「吹雪」といいます。
視界がけぶってしまって歩けなくなることもあり、特に車の運転には危険です。
・雪風巻(ゆきしまき)
旋風にのって雪が吹きまくることを「雪風巻」というそうです。
北国ではよくあることだそうです。
・雪時雨(ゆきしぐれ)
雪まじりの雨が降ったりやんだりしていることを「雪時雨」といいます。
・粉雪(こなゆき)
粉をふりまいたように、細かい雪がぱらぱらと降ってくる。
それが「粉雪」ですね。
・細雪(ささめゆき)
細かな雪が降ったりやんだり、また、それが広範囲にわたってみられることを、「細雪」といいます。
谷崎潤一郎の小説にも『細雪』というのがありますね。
・綿雪(わたゆき)
綿を細かく千切ったような、ふんわりとした小さなかたまりの雪を「綿雪」といいます。
・牡丹雪(ぼたんゆき)
綿雪よりも大きく、まるで牡丹の花のようにふんわりと大きい形をした雪のことです。
・六花(むつのはな)
雪は六角状に結晶することが多いので、雪は別名「六の花」ともいわれます。
・春の雪(はるのゆき)
早春の、とけやすい雪のことです。
田畑をうるおす恵みの水となるので、喜ばれることが多いようです。
・雪の花(ゆきのはな)
山をおおう雪、そして木の枝に積もる雪の景色を遠くから眺めると、まるで白い花が咲いたように見えることから、「雪の花」という言葉が生まれました。

・雪華(せっか)
ちらちらと降る雪片を花にたとえて、「雪華」というんですね。
・根雪(ねゆき)
降り重なった雪は、表面はとけても、下積み部分はなかなかとけません。
そんな積雪が降り固まって春まで残っていることを「根雪」といいます。
・新雪(しんせつ)
積もったばかりの、ふわっとした軽い雪のことです。
やわらかくておいしそうなので、スプーンですくって食べてみたくなりますね。
・しまり雪(しまりゆき)
きめ細かい雪が降り積もり、固くしまった感じになることがあるそうで。
そんな状態の雪を「しまり雪」というのですね。
・ざらめ雪(ざらめゆき)
降り積もった雪の表面がとけ、その後また冷えて固まると、ざらめ砂糖のようにザラザラした感じになります。
それが「ざらめ雪」です。
・べと雪(べとゆき)
水気が多い雪、だけどサラッとしておらず、べとべと粘った感じのする雪のことです。
・雪紐(ゆきひも)
木の枝や塀に積もった雪がずり落ちて、紐のように垂れ下がったものを「雪紐」というそうです。
・筒雪(つつゆき)
電線などに積もった雪が凍りつくと、電線を包んで筒状になるそうです。
それを「筒雪」というそうですが、首都圏など比較的暖かい地域では滅多に見られない現象ですね。
・冠雪(かむりゆき)
門柱、電柱など、柱状のものに雪が降り積もり、てっぺんに白い帽子や冠をかぶせたように見えることを「冠雪」というようです。
同じ意味の言葉で、「雪冠」(ゆきかむり)というものもあります。
・雪庇(せつひ)
山の稜線から庇のように突き出ている積雪を「雪庇」というんですね。
この庇の部分が崩れて、雪崩を起こすこともあるので、大変危険です。
・水雪(みずゆき)
水分をたっぷり含んだ雪を「水雪」といいます。
降り積もっても、やがてとけてしまいます。
ちなみに、雪がとけることを「雪消」(ゆきげ)といいます。
・小米雪(こごめゆき)
ぱらぱらと降ってくる雪を手にとってみたら、お米をついて砕いたような形をしていた。
そんな雪を「小米雪」というそうです。
「粉米雪」と書くこともあります。
・衾雪(ふすまゆき)
「衾」というのは、布団のようなものを意味する語です。
「衾雪」とは、景色全体をすっぽりと覆い包み、厚く積み重なっている布団のような雪のことですね。
「布団雪」といわずに、ちょっとひねりを利かせて「衾雪」と表現するところが面白いと思います。
・しずり雪(しずりゆき)
木の枝から雪が垂れ落ちることを「しずる」といいます。
そうした雪のことを「しずり雪」というんですね。
「しずる」という言葉は、主に広告の世界でよく使われます。
その場合の「しずる」は、
を指します。
広告写真においては、「しずる感」があるかないかがとても重要視されます。
たとえば──
冷たい飲み物の写真はキーンと冷えておいしそうに見えることが大事。
鍋物などの温かい料理はぐつぐつ煮えておいしそうに湯気が立っていることが大事。
そうした「しずる感」の伝わるビジュアルを提供して五感に訴えかけ、購買意欲をそそるわけですね。
・雪の声(ゆきのこえ)
降る雪が音を立てるわけではないけれど、じっと眺めていると、「しんしん」「さらさら」など、どこからともなく音が聞こえるような気がします。
そういう音を指して「雪の声」というんですね。
・深雪(みゆき)
深く積もった雪のことを「深雪」といい、「しんせつ」または「みゆき」と読みます。
・雪晴(ゆきばれ)
雪がやんで空は晴れ上がったけれど、積雪が残り、真っ白な雪と青い空のコントラストが美しい。
そんな日の天気を「雪晴れ」といいます。
・雪夜月(ゆきよづき)
月が積雪を照らし、あたりが暗いのでいっそう雪が輝いて見える。
そんな情景を、昔の人は「雪夜月」と表現したのですね。
・雪気(ゆきげ)
空はどんよりと曇り、寒気が増して、今にも雪が降ってきそうなことを「雪気」といいます。
●おまけ

・雪の卵
地上4千〜5千メートルの上空にある空気が十分な水蒸気を含み、また、「氷晶核」という微細な塵を含んでいると、その氷晶核を中心として、水蒸気が小さな氷の結晶をつくります。
それは「氷晶」といわれるもので、「雪の卵」のようなものです。
卵の大きさは約50分の1ミリメートルですから、目には見えません。
高度4千〜5千メートルの上空で作られた「雪の卵」が高度3千メートルほどまで落ち、そこに過冷却の雲(零度以下でも凍っていない水滴でできた雲)があると、雪の卵は次第に大きくなっていきます。
大きくなった卵はその後も下降を続け、ほかの卵と衝突して合体しながら、ますます大きくなっていきます。
そのようにして大きくなったものが「雪」です。
雪は成長しながら落下を続けます。
↑速度は秒速1メートル以下なので、かなりゆっくりです。
↑高度2千5百メートルの上空から地上に舞い降りるまで、およそ2時間半かかります。
風があるときは、かなり遠くまで飛ばされます。
横に流されながら飛んでいくのです。
ごく弱い風であっても、地上に到達するまでに17キロメートルも横に流されます。
雪国では、晴れ渡った空からまばらに雪が舞い降りてくることがあり、これを「風花」というそうです。
遠い空で生まれた雪の卵が雪雲に出会って「雪」になり、風に運ばれて、地上に暮らす私たちの予想外のところへ舞い降りるのですね。