取材音源を文字に書き起こす作業は、文章力向上に役立つ。
と以前にもお話ししました。
関連記事→テープ起こしをすると文章力が高まる!!
私はライター仕事の一環として、取材音源を文字に書き起こす機会がけっこう頻繁にあります。
聞いたまま書き起こすのではなく、意味が通じやすいようにするために、言葉を整理しながら文にしていくのですが、こうした作業により、文章力は確実に向上します。
もう何十年と続けていることなので、私もわりと上手になったと思います。
その技術を、プライベートの趣味の時間に使ってみました。
Amazon Prime Video某番組のナレーション内容がとても素晴らしかったので、「聞き書き」をしてみたのです。
さすがよくできた番組で、言葉を整理する必要はさほどなく、聞いたままを書き起こすだけで十分に意味が通じる文になりました。
しかし、それをそのままブログに掲載すると著作権に抵触するおそれがあるため、あえてリライトし、編集を加えたものを、ここにご紹介したいと思います。
この番組のエピソード12「禅」より、聞き書きしたものです。

●禅の極意
禅の極意は、心を無にすること。
Nothing Empty.
それが、The Mind of ZEN. である。
Nothing is All.
無=全 である。
そして、すべては自分の内にある。
Just being.
あるがままにあれ、ということだ。
●禅が導く「悟りの境地」
今、禅は世界中に広まり、人々の意識を変え続けている。
禅を通じて、心を集中する術を学ぶことができる。
たとえば、座禅を組むことで集中力を高め、人間の限界を超えた偉業を成し遂げられる。
スティーブ・ジョブスも禅との出会いで覚醒した一人である。
彼は禅を通じて自分を見つめ直し、安らかな心で生きる「悟りの境地」を目指した。
そして、カリスマ的なクリエイティビティと、シンプル極まる革命的なプロダクトを世に送り、社会を一変させた。
禅は内なる力を解き放つ。
そのバイタリティを体得してはじめて、見えてくる世界がある。
●禅と茶の湯の深淵深遠なる宇宙観
禅は仏教の一派である。
禅が中国から日本に渡来したのは鎌倉時代。
それは戦国時代を戦い抜く武将たちが社会の中心に躍り出た時代だった。
禅と共に日本に渡来したのが、茶の湯である。
茶の湯は、禅の深淵深遠なる宇宙観を一杯の茶にまで凝縮した、当時最先端の文化であった。
鎌倉時代の禅僧たちは、中国渡来の最新知識を手にした貴重な存在であり、禅寺は舶来の高度な文化が集まる場所であり、人々の社交の場でもあり、最先端の情報に触れるための窓、知識や教養を得るための学びの場でもあった。
茶の湯は禅を通じて心を伝えるすべであり、心を磨く修行であるという哲学的な側面を有している。
自分を見つめ直し、本来の自分に立ち戻ろうとする禅の精神が、嗜好品であるはずのお茶を崇高な哲学にしたのだ。
それすなわち「今に心を尽くす」ということ。
一つひとつの小さな所作に心を入れ、一服の茶を点てる。
茶人は日々これを繰り返すからこそ、細やかな変化を感じ取ることができる。
今この時と向き合うからこそ、移ろう時の表情をありありと感じ取ることができる。
そのようして日本人は暮らしの中に崇高な美を見いだした。
茶の湯は、死と隣り合わせに生きる武将たちに深く浸透し、その深淵深遠なる宇宙観が心の拠り所ともなっていった。
茶の湯を愛する武将たちは一杯の茶を通じて自分の心を見つめ、今この時を深く味わった。
永遠とは物質ではなく、精神にしか見いだすことのできないもの。
茶室の質素な造りは、そうした禅の精神のあらわれであり、茶は「喫する禅」だった。
掌におさまる小さな茶碗に、宇宙の断片としての重みがある。
そのとき、わずかな空間の茶室は宇宙全体とつながる。
日本人の心はここにこそある、と言ったのは岡倉天心、またの名を岡倉覚三である。
約100年前に岡倉天心がニューヨークの地で著した『The Book of Tea』という書物には、美しく繊細な日本人の生活が茶を通じて綴られている。
そこにある言葉の数々が、移りゆく時の気配、目に見える四季の情景はもちろんのこと、風が運ぶ花の香りも季節の折々で違い、同じ瞬間はふたつとない、ということを伝えている。
すべては移ろう無限の中にあり、永遠は今ここにある。
儚いものを夢見、美しくも愚かしいことに思いを巡らせよう、と岡倉は言う。
これこそが禅の本質、エッセンスなのである、と。
かつて武家社会に浸透し、日本の精神文化の根底を築いた茶の湯の心。
それは、日本の精神文化の根底をなしていった。
茶の湯の心、そして禅の思想は日本人のこころに深く根ざし、今も人生を深く味わう手がかりとなり続けている。

●禅僧の修行
山梨県に、乾徳山恵林寺という600年以上の歴史をもつ禅寺がある。
この禅寺には、命を尊ぶ習慣が息づいている。
僧たちは朝の食事から飯粒を少し皿に取り分け、庭にやってくる野鳥に与えるのだ。
日常の行いが修行そのものであるという生活が営まれている。
寺の掃除など、日々の雑事さえも大事な修行ととらえ、一つひとつ丁寧に行う。
禅僧も茶人も、日々同じことを繰り返す。
修行としてその道を究めるからこそ、彼らは日々生じる細やかな変化を感じ取ることができる。
何気ない日常の断片を大事にしてこそ、日々は輝きを放つのだ。
●禅の食事
禅寺を訪れ、禅僧の食をいただいて英気を養ってみる。
一汁一菜の質素な食事である。
沢庵は専用の器に取り分けてからいただく。
最後にお茶と沢庵で器を洗うのが禅の作法で、じつに合理的なシステムだ。
器を重ねれば、再びコンパクトに収まる。
禅のミニマリズムは食にも及んでいる。
ちなみに、うどんは禅のご馳走である。
静かに食べることが基本だが、うどんだけは音を立ててよい。

●禅の石庭、禅の窓
京都・龍安寺の石庭は、わずか15個の石と白い砂だけで構成された禅の庭である。
Zen Garden、それは簡素な美が織りなす小さな宇宙だ。
構築するのではなく、削ぎ落としていくことで、ミニマルな美の世界を創出しているのだ。
そして、その美しさを通じて、禅の思想を伝えている。
龍安寺の石庭では、白砂の大海原に浮かぶ島が銀河の星々をあらわしている。
そこに見いだされるものは人によってさまざまである。
余白の中に何が見えるのか。
禅の庭を眺めることにより、その時々の偽りのない自分の心を知ることができる。
禅の庭は、見る者の心を映し出す鏡なのである。
そしてまた、源光庵には参禅道場があり、悟りの境地を語りかける庭がある。
同じ庭に面した2つの窓。
四角い窓は迷いの窓とされる。
その隣の窓は角がとれて円くなり、円熟と悟りの境地をあらわしている。
心が変われば、同じ風景を見つめていても見いだされるものは変わる。
この二つの窓は、見る者の心のかたちを象徴的にあらわしている。
●禅と現代アート
広島県の神勝寺に、禅と庭のミュージアムがある。
その一つが「洸庭」といって、海に浮かぶ船をイメージした建物である。
現代彫刻家による作品で、これはお寺の広大な敷地の中に建つ禅のパビリオン、禅のアートミュージアムだ。
禅の思想を現代的に解釈した作品であるとも言える。
その建物のもとで眺める庭園はクラシックな趣だ。
新旧の対比が不思議と調和している。
巨大なボートのような建物のまわりには海をあらわす石が敷かれ、波を表現する珍しい植物が躍っている。
●禅と芸術の密な関係
禅と芸術の結びつきは、過去の時代から密接だった。
かつて僧たちは、悟りを得た者たちの生き様を絵にして伝えた。
禅宗の始祖といわれる達磨はインドから中国へ渡り、厳しい修行の果てに悟りをひらいたとされる。
達磨は座禅を修行の中心とし、そこから自分の心を見つめる禅の長い道のりが始まった。
見かけを飾るのではなく、「知恵と徳によって荘厳であれ」と説いた達磨の教え、すなわち「荘厳堂」という言葉はつとに有名で、多くの掛け軸になっている。

●まとめ
禅とは、日常の小さな出来事や儚いものを尊び、そこに偉大な精神を見いだそうとする日本独自の世界観・宇宙観。
今を大切に生きようとする人々にとって、一服の茶も精神を磨く道となる。
それは美しくかけがえのない一瞬であり、永遠の道でもある。




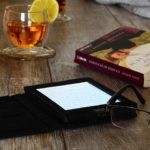











































≪…『The Book of Tea』…≫から数の言葉ヒフミヨ(1234)の[シンタックス]と[セマンティックス]を『HHNI眺望』するのは・・・
[ 朝の光と心の静けさ ―岡倉天心の言葉に学ぶ― ]で・・・