吹く風の種類をあらわす言葉は豊富です。
私たちが日常使う言葉の中にも、風に関する語はいろいろあります。
慣用句にも「風」が用いられています。
風雲急を告げる
風穴をあける
風上に置けない
風の吹き回し
風を食らう
風のたより
先輩風を吹かす
ね、いろいろとありますね。
風にまつわる言葉について、もう少し考えてみましょう。
風にまつわる慣用句

●風雨にさらす(ふううにさらす)
風雨とは、風と雨とを指す語です。
「雨まじりの風」という意味ですね。
「風雨にさらす」という場合は、風雨を「ふうう」と読みます。
「雨風(あまかぜ)にさらす」と言うこともあります。
いずれも意味は同じで、風雨を避ける物が何もない所に置いて野ざらしにすることです。
つまり、きちんと面倒を見ずに放ったらかしにしておくことを言うわけですね。
●風雪に耐える(ふうせつにたえる)
世の中の厳しい試練に負けず、頑張って乗り越えていくことを、「風雪に耐える」と言います。
●風雲急を告げる(ふううんきゅうをつげる)
情勢が不穏で、大変動が起こりそうな状態であること。
今にも大きな変動が起きそうな、さしせまった情勢であること。
というように使われます。
●風穴をあける(かざあなをあける)
行き詰まった状況を打破するため、また、閉塞感のある組織などに新風を吹き込むためにアクションを起こすことを「風穴をあける」と言います。
●風上に置けない(かざかみにおけない)
「風上にも置けない」と言うこともありますが、「風上に置けない」が本来の言い方です。
「風が吹いてくる方向に悪臭を発するものを置くと、風下では臭くて困る」、という意味ですね。
↑卑劣な行動をする者をののしっていう言葉です。
たとえば、
と言えば、同じ男として認められない、仲間として扱えない、ということになります。
●風の吹き回し(かぜのふきまわし)
「風の吹き回し」というのは、「その時々の具合や加減」を意味する言葉です。
というように使いますね。
その場その場の状況次第で変わるため、物事の運びや態度が一定していないことを指すので、「褒め言葉」とは言えないものの、「けなす言葉」というわけでもありません。
強いて言えば、「揶揄する言葉」といった感じでしょうか。
気の置けない友人や仲間、家族など、好意を持つ相手に関して使える言葉です。
●風を食らう(かぜをくらう)
「風を食らう」というのは、「あわてて逃げるさま」のことです。
というように使います。
悪事が露見した場合など、事態を察知したとたんに、あわてて逃げだすことを意味します。
●風のたより(かぜのたより)
「どこからともなく伝わって来たしらせ」「噂に聞いたこと」などを「風のたより」といいます。
というように使います。
●風を吹かす(かぜをふかす)
「風を吹かす」とは、「わざとらしいみせかけのそぶり」を意味します。
知ったかかぶりをする人を揶揄するときなど、
というように使うとよいですね。
ちょっと年上だからといって尊大な態度をとる人には、
と言ってやりましょう。
官僚、警察官、役所の職員などの公務員に横柄な態度をとられたら、
と言ってやりましょう。
●風とは空気の流れのこと

風というのは不思議なものですね。
とらえどころがなく、でも確かに肌身で感じられるものです。
なんて思ったことはありませんか。
子供の頃、誰もが一度はそんな質問をして親を困らせたことがあるかもしれません。
お父さんやお母さんにそう教えてもらった人は幸せですね。
「あっ、そうか!! 言われてみれば確かに、空気が流れているから風を感じるんだ!!」
と一瞬で腑に落ちたでしょう。
「知ることは楽しいな」と、学ぶ喜びを実感したことと思います。
そこでさらに突っ込んで、
としつこく食い下がった人もいるでしょう。
私もその一人です。
と教えてくれたのは、学校の理科の先生でした。
それを聞いて私は、「ふーん、そういうものなのか」と思っただけでした。
としつこく追究する頭があったら、もう少し理知的な人間に成長していたかもしれません。
大人になった今、もし小さな子にそう訊かれたらどう答えればいいのだろう。
そう思って、ちょっと調べてみました。
●大気は気圧の高いところから低いところへ向かって流れる
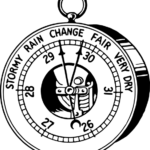
空気は気体です。
気体には、それ自体の重みを示す圧力というものがあり、これを「気圧」と言います。
気圧は、温度や体積の影響を受けます。
たとえば、空気を加熱すると、温度が上昇しますね。
温度の上昇にともない、空気が膨らんで体積が増します。
すると空気の密度が低下します。
こんなふうに、気圧の差によって動きが生じているのです。
ですから、風が吹く理由をより正確に言うなら、
ということになりますね。
●海陸風の吹く家

私がかつて住んでいた家は、東側に海、西側に山があるという立地でした。
日中、東側の窓を開けると海風が吹き込み、西側の窓から抜けていきます。
夕方から夜は、西側の窓から風が吹き込み、東の海のほうへと抜けていきます。
↑こういうのを「海陸風」と言うそうです。
陸と海とでは、太陽による暖まり方が違います。
陸のほうが海よりも暖まりやすいのです。
太陽が出ている日中は、海よりも陸の大気の温度が高まり、そこに上昇気流が生じるため、その空いた隙間を埋めるかのように、海から陸に向かって空気が流れ込みます。
↑これが「海風」ですね。
太陽が沈むと、陸は急速に冷えます。
海は陸に比べて冷えにくいので、今度は海のほうに上昇気流が生じます。
すると、今度は陸から海に向かって空気が流れ込みます。
↑これが「陸風」です。
この「海陸風」というものを、私は毎日の生活の中で体感しました。
家の中を風がさあっと駆け抜けていくのは、とても気分がいいものです。
そしてまた、朝晩1回ずつ、風がまったく吹かない「凪」の状態があることを知ったのも、なかなか味わい深い体験でした。
当時の私は、こう思っていました。
と。
でもそうではなかったのです。
というのが正解なのでした。
●夏と冬の季節風

「海陸風」は年間を通じて吹きますが、
というのは面白い現象です。
夏は太陽の日差しが強いので、陸がどんどん暖まります。
ですから、頻繁に上昇気流が生じ、その空隙に引き込まれるようにして、海から陸に向かって強い風が吹くのです。
冬は太陽の日差しが弱いので、夏場ほど陸は暖まりません。
海洋は陸部ほど暖まりにくい反面、冬場も冷えにくいので、そこに上昇気流が生じます。
すると、陸部によどんでいる重い空気が海に向かって流れ込むのです。
こうした気象現象を、夏と冬の「季節風」と言うそうです。
●まとめ

風にまつわる言葉の数々を紹介するとともに、今回は少し科学的な話もしてみました。
最後に、身近な例をひとつ加えておきます。
冬場など、暖房の効いた部屋から廊下に出ようとして扉を開けると、部屋の暖かい空気が冷たい廊下にさあーっと流れ出す、ということがよくあるでしょう。
そのため、「空気は暖かいところから寒いところへ向かって流れていく。風が吹くのも、これと同じことだよ」と誤解してしまうことがあるようなのです。
しかし、地上全体という広大な空間においては、事情が異なります。
空気それ自体に重みがあって、軽くなったものは上に行き、重くなったものは下に行く、という流れが生じているのです。
だから風が吹くんですね。
















































