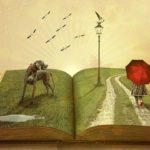と思いつくまま書き出していくと、それも読書習慣の一部となります。
どんな本を読み、どんなことを考え、どこに感動したのか。ということを記録に残しておくことにより、貴重な思い出のストックができます。
わずか数行のメモであっても、あるとないとでは大きく違います。
私の経験からいって、それは写真アルバムにも匹敵する「幸せの思い出貯蔵庫」です。
私の貯蔵庫の中から、いくつかご紹介したいと思います。
ご笑覧いただけますなら幸いです。
●『レトリックの本』JICC出版局(現 宝島社)
『レトリックの本』
『みんなの文章教室』
『文章・スタイルブック』
『珍国語』
──これら4冊のシリーズ本(別冊宝島)は、80年代に立て続けに刊行されました。
いずれも名著だと思います。
文章を書くことに関心のある方はぜひご一読を。
なかでも特に、『レトリックの本』は、変奇な文を集めている点がユニークで面白い。
私が特にいいなと思ったのは、写真家の荒木経惟さんのアラーキーな文です。
逸脱しまくりですよ〜!!
本書は発行当時の人気作家(椎名誠、糸井重里、嵐山光三郎など)から多数の例文を引いています。
今読むとやや古びた印象の箇所もありますが、例文が示す独特の文体と、それを編者が分析する力は現在も十分通用するもので、ものすごく内容が濃い力作、労作であることが伺えます。
井筒三郎さんという方がこの本の全体を統轄しているようで、私など「まいりましたっ」と平伏したくなる思いです。
しかし井筒さん単独の著書は見当たらず、その後どのようなお仕事をなさったかについても不明です。
残念至極。しごく残念。
●『その日本語、ヨロシイですか?』新潮社校閲部 部長 井上孝夫著
目次
第1章 校閲よ、こんにちは
第2章 調べ方の調べ方
第3章 ルビは難しい
第4章 嗚呼!漢字
第5章 仮名づかひ今昔
第6章 グローバル時代の翻訳
第7章 その日本語、間違ってます!?
第8章 その日本語、ヨロシイ!?
第9章 死語の世界
第10章 出版と日本語と校閲と
校閲というハードなお仕事をなさっている部長さんが書かれた現場発のレポート、という感じの本です。
と編集者や著者にお伺いをたてるのが校閲者の仕事である、とのことですが、
と私などは感心しまくりです。
だって、校閲のお仕事って本当に大変そうなんですよ。
日本語の正しい使い方を熟知していなければならないし、歴史・科学・文学・音楽・美術、いえそれだけではなく要するに世界全般について、事実に反する記述があれば修正を促すだけの知見がないと務まらないのです。
正確を期すために各分野の資料にあたって調べていらっしゃるそうですが、もとより博覧強記でなければできない仕事でしょう。
作家の多くが、校閲者の方々を頼りとし、尊敬しているそうです。
私もたまに校正の仕事を請け負うことがあるので、近年、日本エディタースクール校正部門を受講し、修了証書をもらいました。
校正者としては全然たいしたことのない私ですが、いえ、だからこそなのですが、この方面は引き続き勉強していきたいと思っています。
●『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』神田桂一・菊池良著
全100篇のパスティーシュ集です。
Amazonのヒットチャートで見て即買いでした。
私も文体模写を勉強中ですから、こういうの大好きっ!
おおいに楽しませてもらいました!!
という説があります。
でも、文体模写などされて茶化されるのはイヤ、という作家さんは多いかもしれません。
「そんなの知ったことか!!」と強気の姿勢で臨まなければ、パスティーシュはできません。
そうした意味で、本書は潔いよいものを感じさせます。
最初の1篇は
で始まります。
続いて──
スーザン・ソンタグ「反カップ焼きそば」。
迷惑メール「件名:突然ですが、カップ焼きそばを相続しませんか?」
など、興味深いタイトルが続々と登場します。
この本の著者は守備範囲が広いようですね。
テレビや雑誌にも目配りがきいていて、ほんと感心します。
ところで、文体模写をするには、その作家の本を何冊も読み込む必要があります。
私は本書を読みながら、
と、そんなことばかり考えていました。
「火花」の模倣、上手ですね。
村上龍と林真理子のはダメでした。
あまり読んでいないのかなと思いました。
村上龍×坂本龍一の対談模写は、かなり笑えます。
本書を読了後、ほかの本を読むと、いつもとは違う感覚で活字を追っている自分に気づきます。
すべてが文体模写っぽく思えて、どこかにおふざけやオチが仕込まれているんじゃないかと用心しながら読み進めていたりするんです。
●まとめ
今回は、以下の3冊をご紹介しました。