会話でも文章でも、「の」という助詞を連発されると、相手の言わんとすることが理解しづらいものです。
「の」と「の」の間が短ければ、まだいいのです。↓
↑読みづらいけれど、理解はしやすい、という気がします。
しかし、「の」と「の」の間が長くなるにつれ、読みづらさが増します。↓
読みづらいし、何を言おうとしているのか理解するのに時間がかかります。
安易に「の」を使ってはいけないということですね。
では、どのように使えば良いのか、一緒に考えてみましょう。
●余計な「の」を削れば、ピントが合う
●ソフトな響き、だけどわかりづらい
「〜が」を「〜の」と言い替えると、響きが柔らかくなることがあります。
ただし、「の」の使用法として適切でない場合もあります。
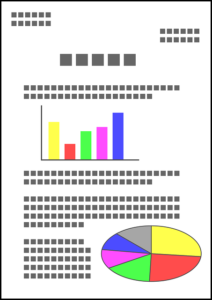
●何なの、その「の」は?
「こと」や「もの」を表す「の」なのか、あるいは、「〜なの」「〜なのよ」「〜なのです」という意味なのか、判別しにくい場合もあります。

●ソフトな響き、だけど判断に苦しむ
「あなたの財布」「私のお金」というように、所有を示すために「の」を用いているのか?
いや、そういうわけではなさそうだが、本当はどうなんだ?
と判断に苦しむ場合もあります。
(または、○○先生について書かれた本を書店で探しました。)
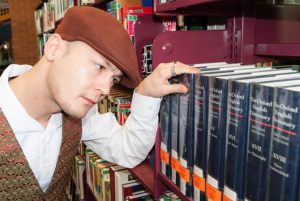
<解説>
・安易に「の」を使うと、思わぬ誤解が生じることがあります。
・「所有を示す」「こと・ものなどを表す」「断定・質問を表す」場合は良いとして、それ以外の「の」は、できるだけ他の言葉に書き換えるようにしましょう。誤解を防ぐためです。
<補足>
・「所有」「こと・もの」「断定・質問」に当てはまらなくても、「の」をそのまま活かしたほうが良い場合もあります。
たとえば──

例文2よりも例文1のほうが、「こなれた」表現といえるでしょう。














































