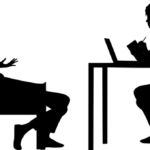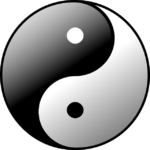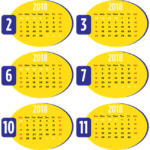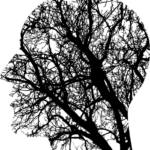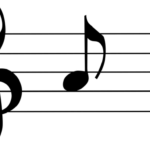私はこれまでに、十数篇の小説を書いた経験があります。
そのうちの2篇は『三田文學』という文芸誌に掲載してもらうことができ、これがおおいに励みになりました。
これからも書いていきたいと思っています。
小説を書くうえで私が特に意識するのは、どのような文体にするかという点です。
文のスタイルや筆致を自由自在に使い分ける、なんてことは難しくてとてもできませんが、力のおよぶかぎり挑戦するようにしています。
私がまだ知らない書き方やコンセプトもあるはず。調べてみよう。実作に活かしてみよう。──というように文体研究のようなこともしています。
そうした過程で、さまざまなスタイルの文(小説・詩)に出会ってきました。
文体やその表現方法の概念を定義しながら解説する文(研究書)や文芸用語もいろいろと知りました。
たとえば、「写実主義(リアリズム)とは、現実を尊重し、それを美化せず理想化もせず、あるがままに描写しようとする立場」というような解説文ですね。
こういうものに出会うと、とても興味をひかれ、もっと知りたい、もっと、もっとと、のめりこんでしまいます。
そんなふうにして集めた解説や文芸用語を、私なりにまとめてみました。
ご興味をお持ちの方はぜひご一読いただけますよう。

文芸表現や文体に関する解説と文芸用語
モチーフ
主題。作品を創作するにあたっての動機となるもの。
パトス
情熱。想念。
カタルシス
カタルシスとは、アリストテレスが『詩学』の中で用いた言葉で、「たとえば悲劇を観る観客は、精神的動揺を体験することにより日頃の精神的抑圧が浄化され、さっぱりとした感じになる」というようなことを指す。
ペダンチック
衒学的。故意に難解な用語を使ったりして学識をひけらかすこと。
ディレッタント
好事家。創作活動に真剣に取り組むのではなく、趣味や道楽として芸術を愛好する人々。
アイロニー
皮肉。微妙な、隠された嘲笑。
エスプリ
精神。機知に富む精神の働き。
リリシズム
抒情性。主観的な情緒を直接に表現すること。
デフォルメ
描く対象であるところの人や物の自然な姿を、作家が特殊な見方をして変形することにより、その特殊な感覚を強調すること。
デカダンス
倦怠感や虚無感を持ち、懐疑的であり、異常な刺激や官能的なものを求める傾向。
19世紀末フランス文芸の一派にデカダンス派があり、ボードレール、ベルレーヌ、ランボー、ワイルドなどがこれにあたる。
日本では、永井荷風、谷崎潤一郎、太宰治、織田作之助、坂口安吾、野坂昭如、吉行淳之介らがこれにあたるとされている。
人道主義
人類愛に基づき、人間の平等と人類全体の福祉・平和を目指す立場。
博愛主義ともいわれ、トルストイが唱えた「キリスト教的博愛主義」が代表的である。
日本では、徳冨蘆花、武者小路実篤、有島武郎らがその影響を受けた。
自然主義
現実をそのままの形で描写することを本旨とする立場。
19世紀後半、自然科学の発展に影響されたフランスの作家ゾラの提唱するところで、その他にモーパッサン、ハーディ、ハウプトマン、ゴンクール、ロシアのツルケーネフなどがいる。
日本では、島崎藤村、田山花袋、徳田秋声、岩野泡鳴、正宗白鳥らがいたが、科学的な面は希薄であり、個人のシンジョウ探求する傾向が強くあったため、後に「私小説」と呼ばれるカテゴリーへと移行した。
写実主義
リアリズム。現実をあるがままに描写しようとする立場。
現実を美化したり理想化したりしないことで現実を尊重する。
19世紀後半のフランスで起こり、フローベール、バルザックら、ロシアではトルストイがこの派に属する。
日本では、坪内逍遙の『小説神髄』や、二葉亭四迷の『浮雲』があり、これらが近代日本文学の先駆けとなった。
モダニズム
現実主義。
未来派、表現派、ダダイズムなど、第一次世界大戦後に起きた一連の芸術運動を総称して「モダニズム」という。
ダダイズム
「ダダ」とは1910年代半ばにヨーロッパのいくつかの地方やニューヨークなどで同時多発的かつ相互影響を受けながら発生した芸術思想・芸術運動のことで、ダダイズム、ダダ主義、あるいは単にダダとも呼ばれる。
第一次世界大戦に対する抵抗やそれによってもたらされたニヒリズムを根底に持っており、既成の秩序や常識に対する、否定、攻撃、破壊といった思想を大きな特徴とする。
「ダダ」という名称は1916年にトリスタン・ツァラが命名したため(辞典から適当に見つけた単語だったとも言われる)、この命名をダダの始まりとすることもある。
ダダの活動は各大都市ごとにあったが、1919年にツァラはアンドレ・ブルトンに招聘されてパリに活動の場を移した(パリ・ダダ)。
その後1922年頃にツァラとブルトンとの対立が先鋭化し、1924年にはダダから離脱したブルトン派によるシュルレアリスムの開始(シュルレアリスム宣言)と前後して、ダダイスムは勢いを失った。
数年後にツァラとブルトンは和解し、ツァラはシュルレアリスムに合流した。
1945年頃、シュルレアリスムも終息した。
カットアップ
カットアップ技法の先例は、1920年代のダダイスムの集まりで生まれた。
それは既存のテキストをランダムに切り刻み、ランダムにつなぎ合わせて、新しいテキストに作り直す、偶然性の強い文学技法またはジャンルのこと。
このような再編は、しばしば驚くような新しいフレーズになることがある。
シュルレアリスム
超現実主義。
意識下にある無意識の世界や不合理・非条理の世界を探求し、そこで得た着想やイメージを形象化しようとするもの。
1920〜1930年代にフランスで起こった文学・芸術運動で、すでに1919年には最初の試みである自動記述(口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスムのこと)が行なわれていたが、1924年にアンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発表し、本格的に運動が始まった。
その宣言の中でブルトンは、オートマティスム(自動記述)をこう定義している。「理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」と。
それはジークムント・フロイトの精神分析とカール・マルクスの革命思想を思想的基盤とし、無意識の探求・表出による人間の全体性の回復を目指すものだった。
ブルトンのほか、ルイ・アラゴン、ポール・エリュアール、フィリップ・スーポー、バンジャマン・ペレらの詩人を中心とする文学運動として始まったが、ジョルジョ・デ・キリコ、マックス・エルンストらの画家やマン・レイらの写真家が参加し、1920年代末頃からスペインやベルギーからもサルバドール・ダリ、ルイス・ブニュエル、ルネ・マグリット、カミーユ・ゲーマンスらが参加。
ダリとブニュエルによる映画『アンダルシアの犬』に見られるように、多岐にわたる芸術運動に発展した。
客観的偶然
シュルレアリストによって発掘されたロートレアモンの『マルドロールの歌』(1868年)の一節「解剖台上のミシンとこうもり傘の偶然の出会い(のように美しい)」は、異なる性質のものを組み合わせたことにより生じる違和感、不安感、驚異の好例として挙げられることが多い。
シュルレアリスムの画家、デ・キリコ、マグリット、エルンストらの作品の特徴ともされる。
一方で、それはロシア・フォルマリズムのシクロフスキーによって提唱された「異化」に近い概念でもあり、ブルトンはこれを「客観的偶然」の概念として提唱した。
すなわち、2つのものが偶然に接近し出会うことによって「現実の中に潜む超現実が露呈し、不可思議(驚異)が現出する」瞬間があるとしたのである。
「コラージュ」と呼ばれる技法も、同様の発想に基づいている。
エルンストはコラージュ作品を絵画としてだけでなく、小説と組み合わせて「ロマン・コラージュ(コラージュ小説)」として発表した。
こうしたエルンストのコラージュについて、アラゴンは「挑戦する絵画」と題する評論を発表した。
キュビスムのコラージュ(パピエ・コレ)、そしてシュルレアリスムのコラージュの発想から、後に写真や映像の分野でいう「モンタージュ」(いろいろの断片を組み合わせて、ひとつの場面をつくること)や、それを立体的に広げる「アサンブラージュ」の技法が生まれることになる。
実存主義
現実の人間存在を文学の中心に据えて描く立場。
実存主義を唱えた哲学者はデンマークのキルケゴールをはじめとして、第一次世界大戦後のハイデッガーなどである。
哲学者・文学者としては、サルトル、ボーヴォワール、カミュなどが代表的である。
日本で実存主義を意識した文学者として挙げられるのは、椎名麟三、埴谷雄高、野間宏などである。
耽美主義
美を至上の価値ととらえる立場。
ワイルド、ボードレール、北原白秋、吉井勇、永井荷風らがこの派の作家として挙げられる。
パスティーシュ
文体模倣、作風の模倣のこと。
故意に似せたものを「文体模写」と訳すこともある。
広義な意味でのパロディもパスティーシュと呼ばれる。
ストーリーの大筋は先行作品から変更せずに、現代的な文脈で読み替えをするという形式のパスティーシュもある。
パスティーシュを行なうには、その作品を一度分解して、再構築することになる。それは作品に対する侮辱であると同時に、作品や作家に対する大いなる敬意の表明にもつながる。
穿ち・戯作(げさく)
江戸時代の中期から後期に流行した通俗小説類、つまり「戯作」における重要な表現法の一つが「穿ち」であった。
それは本来「穴をうがつ(穿つ)」とか「穴をいう」ことの意で、この場合の「穴」とは社会生活万般においてみいだされる欠陥を指し、それが個人的に現れる場合はその人の癖や気質を指すことになる。
「穿ち」はまた、その欠陥を鋭く指摘することで、ややもすれば気づかれずに放置されている穴をいち早く指摘するときに、その「穿ち」が賞賛される。
「穿ち」の姿勢はおおむね無責任であり、あくまでも笑いのための発想法である以上、「風刺」や「教訓」との間に懸隔を置く。
ユーモア、笑い、滑稽、風刺、穿ち、デフォルメ、寓意などをまとった表現でもある。
その一つであるデフォルメとは、つまるところ、誇張をもってする笑殺の一手段であり、その誇張は、鋭い観察の裏付けがあってはじめて笑いに昇華する。
掌編
掌編小説は、短編小説よりもさらに短い作品を指す。(描く内容・ジャンルは多岐にわたる)
「短い短編小説」であるショートショートよりも短い小説(story)とされるが、散文詩的なものもあり、明確な基準はない。
掌編小説という名称は、中河与一が名付け親だとされ、それまでは、岡田三郎が「二十行小説」、武野藤介が「一枚小説」などと呼称していた。
短編小説や中編小説にも、ごく短い小説が連続する体裁を持った作品はあるが、掌編小説は、より長い作品の要約や抜粋、一部分や小品文ではなく、それ自体が単独の物語として完結するものである。
掌編小説は、日本文学の和歌・俳句・川柳の伝統に鑑みて、日本人に合っている文学形式だと言われる。
しかし、形式が短いからといって、内容まで小さく短い小品文となってはだめで、小説になっていなければならない。
これは十七文字の俳句が、千万言を費やした風景描写よりも力強く広大な世界観を持つ場合があることと同様である。
マジックリアリズム
魔術的リアリズムともいう。
文学や美術で、神話や幻想などの非日常・非現実的な出来事を緻密なリアリズムで表現する技法。
ファンタジーは現実とは異なる架空の世界を舞台にすることで、非現実的な現象を違和感なく描いたもの。一方でマジックリアリズムは、現実的な世界を舞台に非現実な現象が起こる。
超常的な現象が「当たり前」として描かれることで読者に不思議な感覚を与える、そこが魅力だとされている。
ハードボイルドとノワール
文芸用語としての「ハードボイルド」は、むだな修飾を極度に省き、スピーディーかつ荒いタッチで事実を積み上げていくスタイルのことで、転じて「冷酷」や「非情」といったニュアンスを持つ作品を指す語として用いられる。
暴力的・反道徳的な内容であっても批判を加えず、客観的で簡潔な描写で記述する手法・文体のことでもある。
ハードボイルド文体は、1920年代のアメリカで始まった。アーネスト・ヘミングウェイの作風などがその一例である。
ミステリの分野のうち、従来あった思索型の探偵に対して、行動的でハードボイルドな性格の探偵を登場させ、そういった探偵役の行動を描くことを主眼とした作風を表す用語として定着した。
「ハードボイルド」という語は元来、ゆで卵などが固くゆでられた状態を指すことから、転じて、感傷や恐怖などの感情に流されない、冷酷非情、精神的・肉体的に強靭で、妥協しない人間の性格を表す。
今日ではミステリのサブジャンルとして扱われるのが一般的だが、サスペンスや一般小説などの主人公をハードボイルド風の文体で描く作品は他のジャンルにもある。
また、ミステリにおいて、主人公は私立探偵とするものが一般的だが、必ずしも主人公が私立探偵であることがハードボイルドの条件ではない。
さらにまた、行動的な探偵が主人公であるが、ハードボイルドとは対照的な性質で非情さを前面に出さず、穏健で道徳的な作品は「ソフトボイルド」と呼ばれる。
ハリウッドでは第二次世界大戦中から多くのハードボイルド・スタイルの映画が作られた。
そうした映画についてフランスの映画批評家・脚本家のニーノ・フランクが「フィルム・ノワール(暗黒映画)」と呼んだことから、映画においては「ハードボイルド」よりも「ノワール」という用語で語られることが多い。
「ノワール」はその後、文芸用語としても使われるようになったものの、本来、「ハードボイルド」と「ノワール」を明確に区切るラインがあるわけではない。
グロテスク・リアリズム
フランソワ・ラブレー、ミゲル・デ・セルバンテス、ロレンス・スターンなどはグロテスク・リアリズム的な作家であるとされている。
1.物質的・肉体的な力の肯定
2.高貴なものを格下げし(パロディ)、なおかつ再生させる
3.生と死・新旧・始まりと終わりなど、両面的な価値をもつ
という特徴をもつ。
中国にもグロテスク・リアリズムの文芸作品はあったとされている。
そこに描かれているのは、猥褻でグロテスクな殺人、不倫、おかしな恋、言語遊戯、異界仙界の話などで、こうした抱腹絶倒のテーマは民衆の過剰なエネルギーを吸収したとされ、これがやがて日本にも伝わり、江戸時代の「読本」に強い影響を及ぼしたとされている。