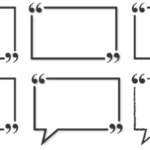【一筆箋の書き方】
贈り物をするとき、または仕事上の書類を送る際など、ちょっとしたメッセージを書き添えておくとよいですね。
そんなときに重宝するのが、一筆箋です。
一筆箋の用紙は8センチ×18センチくらいの比較的小さなサイズで、そこに一言書けるようになっています。
封書や葉書では重たく感じられる場合などに活用すると便利です。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
山田花子
というように、
という流れで書くのが一般的です。
↑メール文の場合も同様ですね。
現代人に必要な文章構成術
一筆箋やメールのほか、SNSへの書き込みなど、短文を書く機会は日常的に結構あります。
これが簡単なようでいて、なかなかむずかしいのです。
わずか3〜4行であっても、どのように話を始め、どのように終えるかを決めなければならないからです。
そこで必要となるのが、文章構成術です。
というように、流れを意識しながら書くと、うまくいきますよ。
序破急
序
導入部
破
展開や転換が起きる
急
結末
起承転結
起
これから述べることの総意を簡潔に伝える
承
具体例を挙げるなどして、「起」を補足する
転
話題や視点を変える
結
「転」で述べたことを踏まえて、結論を述べる
────────────
「序破急」も「起承転結」も、
という基本構造は同じです。
「起・承・結」もOK
「起承転結」の「転」にあたる情報がない場合は、つまり話題の転換をはかる必要がないなら、「起・承・結」でいけばいいのです。
前述の一筆箋にも、「転」はありません。
↑これは典型的な「起承結」の構造ですね。
あえて「転」から書き出すのもOK
作文や読書感想文、エッセイなどをより面白いものにするために、あえて「転」を冒頭に持ってくるという方法もあります。
意外なことから書き出して、「えっ、そんなことってあるの?」と読者の興味をひき、そして、冒頭の「転」につながる「起」や「承」を語っていくわけです。
このような「転・起・承・結」という文型もあること、覚えておくとよいですね。
エッセイなどの情緒型文の場合は、「結」はあってもなくてもよい、という感じです。
倒叙法についても知っておこう
現在から過去へ、時間を逆にさかのぼって叙述することを「倒叙法」といいます。
「倒叙ミステリー」というものもあります。
「刑事コロンボ」や「古畑任三郎」などがそれですね。
まず事件が起こり、犯人が明かされた上で、警察あるいは探偵役が捜査に乗り出し、事件を解決していきます。
犯人とおぼしき人物の行動を分析し、動機を推理するプロセスがたまらなく面白いので、「やったのは、こいつだ」とわかっていても、つい引き込まれて最後まで読んで(見て)しまいますね。
この「倒叙法」というのも、「転」から始める書き方の一種であろうと思います。
●まとめ
論を展開する流れは自由に作っていくことができます。
基本となるのは「序論→本論→結論」という流れで、「序破急」「起承転結」といったバリエーションがあります。
転から書き出すのもOKですし、結論から先に述べたほうがよい場合もあります。
どんな場合にも決して忘れてはならないことは──
これらに留意して、理路整然とした文を作っていきましょう。