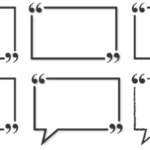本を書くときの文章構成術
書籍原稿のように、長大な文章を執筆するにあたっては、まず全体の構成(骨組み)をきちんと組み立てておくことが大切です。
ビジネス書など、ノンフィクションものの書籍原稿はたいてい、 次のようになっています。
●単行本1冊あたり、4〜10の章を設けるのが適量
●各章のはじめに「扉ページ」を設け、そこにリード文を書く
●各章とも、「章」→「節」→「項」という3段構えで構成する
●「項」の本文ひとかたまりごとに「見出し」をつけて、読みやすくする

本の目次を「分析」してみよう
書籍の目次を見ると、「章→節→項」の構造がよくわかります。
一例として、拙著『言いたいことが伝わる上手な文章の書き方』の第1章の構造を見てみましょう。
例
【章タイトル】
第1章 この文章は、どこがおかしい?
【章扉のリード文】
理解に苦しむ「悪文」を書き換えてみよう
私たちがふだん目にするブログやSNS、雑誌、新聞、書籍、新聞にも、意味がよくわからない「難解な文」がいくつも見つかります。
むずかしい内容だから理解できないのではなく、言葉の使い方が適切でないために、理解に苦しむ文になっているのです。
そういう「悪文」こそ、筆力向上をはかる良い教材となります。
【第1章・第1節の見出し】
「誰が何をしたのか」が、わかりにくい文章例
【第1章・第2節の見出し】
読めば読むほど理解に苦しむ悪文例
【第1章・第3節の見出し】
書かれていなければ、読者にはわからない
【第1章・第4節の見出し】
誤解を誘う、まぎらわしい表現
【第1章・第5節の見出し】
読者の推理によって、意味が変わる文章
↑第1節〜第5節のそれぞれに、いくつか「項」(本文)が設けてあり、
●例文
●ここが残念!!
●改善例
●解説
●補足
といった小見出しがついています。
(ご興味のある方はぜひご購読を!!)