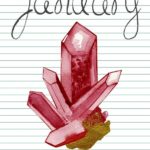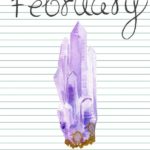3月3日は桃の節句、女の子のお祭りの日ですね。
男子の祭りである端午の節句よりも、桃の節句のほうが、世の中全般で盛り上がっているように感じますが、気のせいでしょうか?
いえ、実際にそうですよね。
小さな女の子だけでなく大人の女性も、3月3日のひな祭りは心浮き立つものがあります。
なんといっても、雛人形と桃の花という取り合わせが華やかで美しく、優雅な気分にさせてくれますし、女の子同士集まっておしゃべりを楽しみたいという気になるのです。
●お雛様をいつまでも飾っておくと、結婚できなくなる?

私もハタチ過ぎるまでは毎年、両親がお雛様を飾ってくれました。
うちにあった雛壇はたしか五段で、緋色の布が掛けてありました。
子供の頃、それは見上げるほどの高さで、天井まで届きそうでした。
精緻な造りの雛人形やお道具の数々がずらりと並んでいるのが何とも誇らしく、明るい未来を約束されているように感じたことを憶えています。
今にして思うと、娘の健やかな成長を願う親心に包まれていたんですね。
ありがたいことです。
3月3日が近づくと、女の子のいるうちではたいてい雛壇を飾っていましたから、近所の女の子たち数人で家々を回ってお雛様を見せてもらい、その家のお母さんがくれる雛あられをおやつにして仲良く遊んだのも、いい思い出です。
でも、翌日にはもう、どこの家にもお雛様がありません。
3日の晩か、4日の朝早くに、片付けてしまうのです。
「お雛様、どこにしまったの?」と母に訊くと、
「押入の天袋に大切にしまったよ。また来年ね」と言われました。
そして母は、
「お節句を過ぎてからもお雛様を飾っておくと、いきおくれになるからね」
なんてことも言っていました。
いきおくれ、つまり「嫁きおくれ」という言葉をまだ知らなかった私は、あわてて訊き返しましたよ。
「お雛様をいつまでも飾っておくと、私どうかなっちゃうの?」と。
母が言うには、
「結婚できなくなるかもしれない」
とのことでした。
びっくり〜!!
子供ながらにショックでしたよ〜!!
ってことはつまり、いいひとに巡りあって恋愛しても、婚約や結婚には至らないということ?
婚期を逃してしまうの?
それって本当のこと?
ただの迷信じゃないの?
大人になった今でも不思議です。
私の場合は、3月3日を過ぎてもお雛様を出しっ放しにするなんてことはなかったにもかかわらず、事実、未婚です。
結婚できない(しない)のはお雛様のせいではないと思うのですが、だとしたら何故、あんな迷信じみたことが言われるようになったのでしょう。
気になります。
私の場合にかぎらず、結婚しない女性が増えている今、また、晩婚化が進んでいる今、その本当の理由が気になります。
●非婚・晩婚が増えている本当の理由

内閣府による「家族と地域における子育てに関する意識調査」では、未婚の若い男女を対象に、さまざまな質問をしています。
その回答を見ると、
「いずれは結婚したい」(52.0%)
「2~3年以内に結婚したい」(10.0%)
「すぐにでも結婚したい」(9.6%)
という結果で、7割以上の人が「結婚したい」と望んでいることがわかります。
なのに、若い世代がなかなか結婚しない(できない)理由は何なのでしょう。
という回答が最も多く、5割以上を占めています。
「希望の条件を満たす相手にめぐり会わないから」
という理由に加え、
「経済的に余裕がないから」
という回答がやはり多かったようです。
男女いずれの場合も、未婚や晩婚の背景に経済的理由があるということですね。
●お雛様を早く片付ければ、娘も早く片付く?
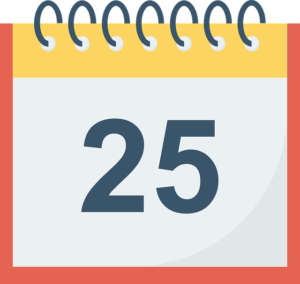
今は晩婚・非婚の傾向にありますが、昔は、女性が25歳を過ぎても結婚せずにいると、
「適齢期を過ぎた」
「嫁きそびれた」
「売れ残り」
などと言われていました。
ですから親としては、娘がまだ若いうちになんとかして結婚させようと必死だったでしょう。
という発想が生まれたのは、そんな事情があったのでしょうね。
●お雛様を飾ったままにしておくと、悪運がつく?

もう一つ、考えられることがあります。
と恐れる気持ちがあったのではないかということです。
というのも、お雛様というものは本来、
ためのものだったからです。
●「曲水の飲」と流し雛

3月3日を「桃の節句」と言いますが、正式には「上巳(じょうし)の節句」です。
桃の花が咲く時季なので「桃の節句」とも言われ、桃の花や菜の花など、自然の生命力をもらって厄災を祓います。
「上巳の節句」は、中国から伝わった「曲水の飲」と、日本古来のお祓いの風習とが合体して起こりました。
昔、中国ではこの日、上流階級の人々が池や川など清流のある所へ行って「流杯曲水の飲」をしたとされます。
↑曲水(水の流れ)に杯を浮かべて、その杯が所定の場所に到着するまでの間に詩をつくって競い合うという、風流な遊びが盛んだったのです。
この風習が平安時代に日本にも伝わり、貴族階級に広まりました。
平安貴族たちはこの日、水辺で詩を作ることに加えて、陰陽師を呼んでお祓いの行事もしたそうです。
↑人間の形を模して作られた紙製の人形(ひとがた)で身体をなでることによって、自分の穢れを人形のほうに移し、それを川や海に流すのです。
このお祓いの道具としての人形が、単なる紙の人形から発展し、押し絵や胡粉塗りを施した豪華なものになっていきました。
↑こうした豪華な人形が、雛人形の原型だとされています。
●お雛様を川や海に流す「ひなおくり」の風習

人形に穢れを移して水に流し、災厄を逃れるという風習は、3月3日「上巳の節句」の節句の行事として、全国各地に広まりました。
今でも地方によっては、3月3日の節句には紙や布で作ったお雛様を携えて野遊び・山遊びをしたあと、お雛様を川や海に流す「ひなおくり」の風習が残っています。
こうした「ひなおくり」の風習があることを知っている家庭では、
と親が心配することもあったでしょう。
しかし、現在一般に販売されている雛人形は効果なので、水に流して捨てるなんて、もったいないことはできません。
と考えるようになったのかもしれませんね。
●きちんと飾れば、お雛様はきっと喜んでくれる

人形は、その持ち主である人物の身代わりともなりうる、ありがたい存在です。
できるだけ大切に扱うことが望ましいといえますね。
お雛様を出しっ放しにするのもよくないけれど、何年も収めったままというのもよくないでしょう。
毎年きちんと飾ってさしあげることにより、お雛様は喜んでくれるのではないかと思います。
お雛様の飾り方
●雛壇の最上段に男女一対の内裏雛(だいりびな)を飾り、背景に屏風、左右に雪洞(ぼんぼり)を置く。
●2段目に、三人官女(さんにんかんじょ)や五人囃子(ごにんばやし)を飾る。
●その下段に左大臣(さだいじん)と左近の桜、右大臣(うだいじん)と右近の橘(たちばな)、三人仕丁(さんにんしちょう)などの雛人(ひなじん)を飾る。
●お雛様のお道具として、ごく小さな箪笥(たんす)、長持(ながもち)、鏡台、針箱、鋏箱(はさみばこ)、重箱、駕籠(かご)、御所車(ごしょぐるま)などを飾る。
●菱餅、白酒、ひな菓子などを供える。
●娘の嫁入り道具のミニチュア版

宮廷で用いられる調度品など、お道具立てが凝っているのも、お雛様の魅力です。
ミニチュアながら、精緻な造りの箪笥、長持、鏡台、針箱、鋏箱、重箱、駕籠、御所車などが飾られるのは、
という親心のあらわれですね。
このようにして飾った豪華な雛壇に、桃の花や菜の花を活けて供え、雛壇の前にお膳をしつらえて、ちらし寿司とハマグリのお吸い物といったご馳走をいただき、白酒を飲んでお祝いするのは本当に楽しいひとときです。
お雛様もきっと喜んでくれるはず。
よいご縁を結んでくださるとよいですね。