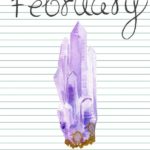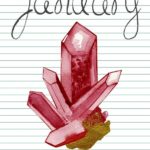秋はご飯がおいしい季節です。
採れたての新米が出回るからです。
しかし翌年の4〜5月にもなると、新米といえども味が落ちるようです。
精米後20日間くらいは鮮度を保てるとされていますが、それ以上経てば、やはりどうしても風味は落ちてしまうのです。
●1度にたくさんのお米を買わない

秋から冬は、収穫したばかりの新鮮な米を食べて「おいしい、おいしい」と喜んでいられたのに、春になって暖かくなるにつれ、だんだんおいしく感じられなくなるのは本当に残念〜!!
いつものお米よりもワンランク上のものに切り替えるとよいのでしょうか?
いいえ、高価なお米が必ずしも味がよいとは限らないようです。
お米を販売する各社各店ごとのブレンドによって味が異なるからですね。
要は、そのブレンドの妙味が自分の好みに合うかどうかということ。
異なる販売元の異なる銘柄を食べ比べて、自分にぴったり合うものを見つけるのがよいと思います。
そして、
というのが賢い方法でしょう。
特に梅雨時は、目には見えない細かなカビが生えることもあるので、
ようにするとよいのでは、と思います。
●おいしいご飯を炊くための水加減

おいしいお米をおいしく炊けるかどうかは、水加減と火加減にかかっています。
まず、水加減についてお話ししましょう。
と私は思っています。
ちょっと固めに炊いたご飯が好きなんです。
お米をとぎ、水気を切ったあとの洗い米は、水気を含んで1割ほどふくらんでいるそうです。
ですから、お米の計量カップで量った米180mlに対し、同じ計量カップで量った180mlの水を加えます。
計量カップ3杯の米ならば、水もカップ3杯です。
↑新米は完全に乾ききっていないため、水分を含んでいるからです。
4〜5月以降は、水加減を少しずつ増やすようにするとよいようです。
●おいしく炊きあげる火加減

ツヤツヤでふっくらしたご飯を炊きあげるには、米の一粒一粒にしっかりと熱が伝わり、ムラなく加熱することが大切だとされています。
その火加減はなかなかむずかしいのですが、昔からよく言われるように、かまど炊きご飯をおいしくする火加減のコツは、
です。
そういう面倒なことは電気炊飯器が勝手に調整してくれるから気にしたことがない〜という方は多いと思います。
たしかに、電気炊飯器はどこのメーカーのものでもたいてい、自動で火加減を調整する機能が付いていますね。
↑中火〜強火で約10分、沸騰するまで炊いたあと、弱火で約15分炊きあげ、最後に約10分蒸らすというように、プログラムが組み込まれています。
ただし、製品によって、炊きあがり具合に差が出ます。
電気炊飯器(5号炊)の場合は、安いものなら6000円くらいからあり、高いものでは10万円ほどします。
↑私の経験からいって、低価格の炊飯器ではやはり「それなりに」しか炊けないようです。
友人宅で晩ご飯をご馳走になり、うちのご飯とはまるで違って、ふっくらとおいしく炊きあがっているのにびっくりしたことがあります。
と友人は言っていました。
聞けば、南部鉄を使用した圧力式の電気炊飯器を使っているのだそうです。
↑食事を終えて後片付けをお手伝いしたとき、その南部鉄の炊飯鍋を洗おうとしたら、手にずっしりと重いので、
と納得しました。
●文化鍋もオススメ

ずっと以前のことですが、まだ電気炊飯器を持っていなかった頃の私は、ガス台に文化鍋を載せてご飯を炊いていました。
ガスですから、自分で火加減を調節します。
という教えをきちんと守れば、いつも間違いなくおいしく炊きあがりました。
↑Wikipediaより引用
●味の落ちた新米をおいしく炊く方法

水加減も火加減もバッチリのはずなのに、炊きあがりの味がいまいちぱっとしないというときは、
を活用してみましょう。
昆布と一緒にお米を炊くと、昆布の出汁が利いたおいしいご飯に仕上がります。
お酒を加える場合は、米2カップに対し、酒を大さじ1くらいの割合にするとよいと思います。
炊きあがったご飯にツヤがなく、なんとなくパサパサした感じになってしまうなら、サラダ油をちょっと垂らしてから炊くとよいようです。
↑米2カップに対し、サラダ油大さじ1くらいの割合がちょうどよいと思います。
●まとめ

新米の季節を過ぎてからも、一年中おいしいご飯を楽しめるよう、いくつかアイデアを挙げてみました。
●1度にたくさんのお米を買わず、1〜2キロずつ、こまめに買い足すようにするとよい。
●おいしいお米をおいしく炊けるかどうかは、水加減と火加減にかかっている。
●米1合に対し、水.1.1〜1.2合くらいがちょうどよい。
●新米を炊くときは、水の量をやや控えめに。
●ツヤツヤでふっくらしたご飯を炊きあげるには、米の一粒一粒にしっかりと熱が伝わり、ムラなく加熱することが大切。
●火加減のコツは、「はじめチョロチョロ、中パッパ、赤子泣いてもフタとるな」。
●炊きあげて約10分蒸らしたあとは、鍋の中身全体を切るようにかき混ぜ、余分な水分をとばすと、いっそうおいしくなる。
●昆布、酒、サラダ油を活用すると、少し古くなって味が落ちたお米もおいしく炊ける。