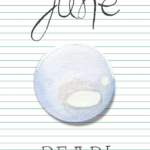10月は年に一度の神様大集会が出雲の地で開催され、八百萬の神がお集まりになるため、全国各地で神々が不在となる。だから神無月というわけですね。
(神様大集会が開かれる出雲の地においては「神在月」(かみありづき)となるようです。)
ちょうどその頃、街ではハロウィーン(英: Halloween または Hallowe’en)のディスプレイをよく見かけるようになります。
魔女、蝙蝠、カボチャなど、黒&オレンジ色というパンチのきいた配色で飾られたショーウィンドーを見ていると、ああ今年もこの季節がやってきた、となんだか嬉しくなります。
そして毎年10月31日が近づくにつれ、日一日と気分が盛り上がっていきます。
この時季はコスプレの準備に余念がない、という人も多いでしょう。
そこでハロウィーンについて少し考えてみるのも悪くないでしょう。
何だったかな〜
何かを祝ったりお願いしたりするものなんじゃない? という人がほとんどかもしれません。
私もそうでした。
そこで調べてみたのです。
意外なことがわかりました。
そして、
●「秋の収穫祭」と「悪霊を追い払う宗教儀式」の融合

ハロウィーンとは元々、古代ケルト人(中央アジアの草原から馬車や戦車と共にヨーロッパへ渡来した民族)から始まったとされています。
それは、翌日(11月1日)の万聖節に備えて悪霊を追い払い、清らかな世界で聖人たちを祝福すること。
そして、今は亡き先祖を我が家に迎え、農作物の豊かな収穫を祝うこと。
ハロウィーンとは、そのための準備セレモニーなのでした。
そうなのです。ハロウィーンって、「鬼は外〜!! 福はうち〜!!」と共通するものがあるのです。
西洋の子供たちが魔女やお化けの仮装をし、「トリック・オア・トリート」(Trick or treat. ご馳走してくれないと悪戯するよ)と唱えながら、近所の家を1軒ずつ訪ねてお菓子をもらうという風習は、日本でならさしずめ、鬼の扮装をした子供たちが隣近所を回って「鬼は外〜!! 福はうち〜!!」と豆をまいて歩くようなもの、といえるかもしれません。
「鬼は外〜!! 福はうち〜!!」
この呪文で悪霊を追い払い、清らかな世界をつくりだして新年を迎える。それが日本の節分です。
西洋でも同じようなことをしていて、それがハロウィーンだったというわけです。
ちなみに、
●古代ケルトのお盆は10月31日

古代ケルトにおいて、10月31日は夏の終わり、そして冬の始まりを意味していました。
そして、この日は死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていたそうです。
先祖の霊を迎えるために蝋燭を灯し、そしてまた、暗く寒い時季になると悪い精霊や魔女が次々と姿を現すので、人々は自分や家族の身を守るために仮面を被り、魔除けの火を焚いていたとのこと。
こうした風習に因み、10月31日の夜はカボチャの提灯を飾り、カボチャのお菓子を作って食べるようになったわけです。
カボチャの中身をくりぬき、中に蝋燭を立てた「ジャック・オー・ランタン(Jack-o’-lantern)」。
あのカボチャ提灯には魔除けの意味があるそうですが、私たち日本人がお盆に迎え火を焚いたり提灯を飾ったりして、ご先祖様が道に迷わずに我が家へ帰ってこられるようにと気を配るのによく似ています。
日本では、お盆の迎え火と提灯。
このふたつは、よく似た存在なのです。
こうしていろいろ知っていくと、ハロウィーンがより身近なものに感じられ、ますます楽しみになりますね。
●現代のハロウィーンは、子供の安全第一

という気持ちは、人々を祭りに駆り立てるのかもしれません。
豊かで安寧な暮らしを希求する思いは世界共通です。
「秋の収穫祭」と「悪霊を追い払う宗教儀式」は、ケルトの地においてハロウィーンという祝祭に発展していきました。
それが少しずつ形を変えながらも西欧各地に広まり、特にアメリカ合衆国で民間行事として根付いたとされています。
現代のハロウィーンは、本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなり、かぼちゃの「ジャック・オー・ランタン」をシンボルに、そして「トリック・オア・トリート」(お菓子をくれないとイタズラしちゃうぞ)を合言葉に、家族や友人たちが集まって楽しく過ごす日となっています。
子供たちは、お菓子をたくさんもらうことを楽しみにしているでしょうね。
可愛らしい小さな子が「ご馳走してくれないと悪戯するよ」と言っているのだから、お菓子をあげなかった場合はどんな悪戯をされても笑って許すべし、とされていますが、それはあくまでも「言葉のあや」でしょう。
子供たちにしても、お菓子をもらえなかったときはがっかりするものの、静かに立ち去るというのがほとんどのようです。
また、いかにハロウィーンといえども、ふだん行き来のない家庭をいきなり訪れるのは危険だという理由から、子供たちに「ご近所巡り」を禁止している家庭も増えているようです。
●キリスト教諸聖人の偉業を祝福する日

11月1日「万聖節」のことにもふれておきましょう。
万聖節(ばんせいせつ)というのは古くからの呼称で、今は諸聖人の日(しょせいじんのひ)と言うことが多いようです。
ともあれ、それはキリスト教における全ての聖人と殉教者を記念する日で、カトリック教会によって祝日と定められています。
カトリック教会の典礼暦によると、
11月2日も万霊節(死者の日)
となっています。
11月1日の万聖節は,イギリス国教会またはカトリック教会のある世界各国で祝いの行事が行なわれますが、中でも盛んなのはカトリック信者の多いイタリアの地において、だそうです。
この日、多数の人が教会ミサに参列し、お墓参りに行くそうです。
カトリックとは異なる教派、というのはたとえば聖公会や正教会などですが、そうした教派・教会においても、「諸聖人の日」に相当する祝日・祭日を定めていることもあるそうです。
ただ、その呼び名や日付は必ずしも一致しないとのことです。
●聖人カレンダーと仏教カレンダー

私はキリスト教の幼稚園に通っていましたが、卒園してからはキリスト教とあまり縁がなかったため、聖人や殉教者について詳しく知りません。
でも、「聖ペトロ」とか「聖ヨハネ」という名は何度となく耳にしていますし、キリスト教が盛んな国々には「聖人カレンダー」というものがあり、1年を通じてほぼ毎日、「今日は聖○○○の日」と記されていることも知っています。
ちなみに、10月31日のカレンダーを見ると、「聖ウォルフガング司教」の名が記されています。
続く11月1日は「諸聖人の日」、11月2日は「死者の日」となっています。
仏教カレンダーではどうなっているでしょう?
今年(平成29年)10月のカレンダーによると、
となっています。
私が数えたところ、仏教「聖人」の名が挙げられているのは年に35日ありました。
西欧に比べると少ないようですね。
その代わりというわけではないのでしょうが、
1月「初詣」「初観音」「初地蔵」「初不動」「針供養」に始まり、
12月「納め観音」「納め大師」「納め地蔵」「終い天神」「納め不動」「大晦日除夜の鐘」まで、
仏教行事は毎月いろいろとあります。
●コスプレは「毒をもって毒を制す」の精神で

さて、話を戻すと──
ハロウィーンは翌日の万聖節を清らかな状態で迎えるために邪気を追い払うことを1つの目的としているわけですから、キリスト教に縁のない私でも、「清らか」ということを少しは意識したいと思います。
魔女や黒猫、骸骨、ゾンビなどに仮装するのも、その本来の目的は、
なんですよね。
コスプレすることにも重要な意味がある、のです。
ハロウィーン・コスチュームをAmazonで探してみました。
私も魔女のコスプレしてみたいなあ。
Amazonで見ると、お値段も案外安いのね〜。
注文はお早めに、ですって。
●まとめの一言

というのが私の感想です。
今年のハロウィーンには邪気を祓って清らかな世界を作り出し、新しい年のはじまりとされる翌11月1日を大切な人々と共に迎えたいと思っています。
10月31日に向けて、あなたはどんなプランを練っていますか。
恋人とふたりだけのハロウィーン、家族で祝うハロウィーンもいいですね。
パンプキン・ランタンでお部屋を飾り、コスチュームとメイクアップをばっちり決めてホームパーティを開いたらどんなに楽しいでしょう。
私も、自分なりに得意料理をいくつか並べ、そこにカボチャ料理とカボチャのお菓子を加えて、友人たちをおもてなしする予定です。
この日に夢や希望や願いを唱えると、いつかきっと叶えられると思うのです。
ハロウィーンと万聖節には、何かそういう不思議な力が強くはたらくという気がします。
私も心からの願いを唱えるつもりです。
幸せを呼ぶ魔法の呪文
アファメーションとは、なりたい自分になるために不可欠とされる「良い思いこみ」をつくることです。それは「肯定的な自己暗示」「肯定的な自己説得」「肯定的な自己宣言」ともされています。
アファメーションの言葉を何度となく口にし、また、見たり聞いたりすることで、良い「マインドセット」がなされるそうです。すると自分の意識や行動が知らず知らずのうちにコントロールされて、言葉どおりの現実をつくっていけるよう、促されるのですね。
私は、次の11箇条をアファメーションにしています。(個人情報に深く関わることは伏せ字にしています。)ご参考までに、ご一読いただけますなら幸いです。
Affirmation
(1)
私は父と母のおかげで生命を享けました。
世界中の誰よりもお父さんとお母さんに感謝しています。
(2)
両親が慈しみこめて育んでくれた、この身体を大切にします。
病気を遠ざけ、芯から健康で美しく、百歳長寿を全うします。
(3)
私は常に弟を支え、弟によって支えられています。
弟の○○とその娘○○の幸せを願い、生涯支えあっていきます。
(4)
私には大好きな人がたくさんいます。
関わりのある皆さんと仲良くし、愛情いっぱいの人生を生きます。
(5)
私は慶應義塾大学および大学院で学び、日本語の専門家になります。
さらに一年間の語学留学をして、英語が自在に操れるようになります。
(6)
私は週3回、バレエ・ダンスのレッスンを続けています。
鋼のように強くしなやかな筋肉としまったボディラインをつくります。
(7)
私は横浜○○に自分の家を持ちます。
素敵な衣食住遊と季節感に恵まれた、理想の生活を実現します。
(8)
私は毎年ヴァカンスで世界の都市や田舎に滞在します。
さまざまな人と文化芸術にふれ、創造力の源とします。
(9)
私は成人して以来、仕事を通じて成長し、経済力をつけています。
近年ついに辿りついた文筆業は、まさに私の天職です。
(10)
私はファンタジックな長篇小説と濃密な短篇小説をたくさん書きます。
世界中に多くの読者を持ち、傑作の感動を分かち合います。
(11)
私にとってものすごくいい男をみつけ、最高の恋と結婚をします。
ふたりなら何処にいても何をしても人生になる。互いに満たし満たされます。