漢字の読み方は、時代によって変化します。
いろいろ調べていくと、
と驚くばかりです。
たとえば「睡眠」という漢字を昔は「すいめん」と読んでいたなんて、びっくりしてしまいますね。
だって、「睡眠」の「眠」の字は、どう考えたって「めん」ではなく「みん」でしょう。

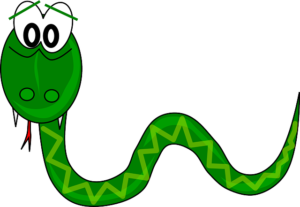
「蛇足」を「じゃそく」と読むのが正しい時代があったというのも、なんだか信じられないような思いです。
「蛇」を音読みすると「じゃ」になることは知っていたけれど、「蛇足」は「だそく」と、学校で教わりましたものね。

「すいめん」が「すいみん」になり、「じゃそく」が「だそく」になっていく過程には、世の中の多くの人が「読み間違い」をしたということでしょう。
みんなで間違えれば、いつしか正解になっていくこともあるのです。
言葉の世界は奥深いものだと、つくづく感じます。
●誤用であっても慣用として定着したもの
↑これらの語は、現代ではもう完全に、新しい読み方にスイッチが切り替わっていますね。

●読み方変化の途中にあるもの

「重複」の正しい読み方は「ちょうふく」であると私は信じているのですが、「じゅうふく」と読んでも間違いではないとされつつあるのですね。
社会が変化するスピードが速まっているので、漢字の読み方も猛スピードで変化しているようです。
●マスコミ各社が頼りとしている「用字用語の手引き」

通信社や新聞社では、各社それぞれに「用字用語の手引き」を作成しているそうです。
といったこ事柄についての基準を設け、その基準にしたがって記事が書かれ、原稿整理や校正といった作業がなされていくわけですね。
ただし、社外執筆者の署名原稿や固有名詞については、基準の適用外とすることが多いのだそうです。
出版社では、「用字用語の手引き」に類するものを作成している例は少ないようです。
例外として、年間の刊行点数の多い出版社では、内部資料として、「書籍校正の手引き」というような印刷物を作成し、編集者や校正者が判断に迷うような点について、社としての方針を具体的に示しているとのこと。
しかしほとんどの出版社は、漢字表記や読み方の統一を図るうえで拠り所となるルールブックのようなものは持っていません。
私も出版社の依頼を受けて原稿を執筆することを仕事とするライターの一人ですが、
などと言われたことはありません。
よって、個々の編集者によって判断基準が異なり、また、出版物によっても判断基準は異なります。
たいていは、
ということが基準といえば基準となります。
●まとめ
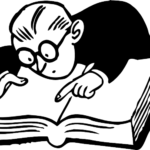
書籍や雑誌の場合と同じように、辞書も、版元が異なれば、掲載されている内容に違いが生じるのは当然のことです。
となると、私たちライターは、複数の辞書を比較検討し、自分なりの答えを導き出すしかありません。
たとえば、「出生率」は「しゅっしょうりつ」と読み、「しゅっせいりつ」と読むのは間違い、と私はブログに書きましたが、「しゅっせいりつ」でもよいとされつつあることを、今ようやく知りました。
現在、ほとんどの辞書が「しゅっしょうりつ」という読み方を記載していますが、いずれは「しゅっせいりつ」とする辞書も出てくるでしょう。
そうなっても慌てないように、言葉の変化をつねに注意深くウォッチしていこうと思っています。
















































