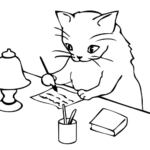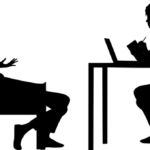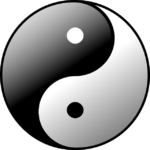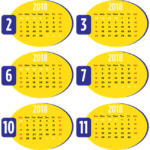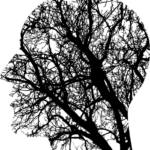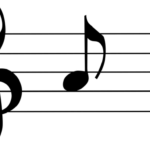この記事の1つ手前の記事は、
に関する美容・健康情報でした。
前記事→牡蠣(カキ)は完全栄養食、貧血気味の女性には何よりの食べ物
という妄想が湧き、遊び心で某作家の文体模写をしてみたのが当記事です。
前記事と当記事、併せてご笑覧いただけますなら幸いです。
さて、まずは文体模写について少しお話ししたいと思います。
文体模写というのは、つまり他人の文章スタイルを真似て書くことです。
そしてこれが、筆力向上におおいに役立つのです。
ですからこれ、暮らしに役立つ歳時記情報をゲットしながら、ついでに言葉力アップグレードをはかるという、一粒で二度おいしい企画なんですね。
年間シリーズ企画としてお届けする予定で、今回はその第8回目、町田康氏バージョンをお届けします。
暮らしに役立つパスティーシュ(文体模写)
第8回・町田康氏バージョン
酒好き&B級グルメのあの作家ならば、きっとこう書くだろう

「牡蠣シャブリvs.牡蠣ギネス」
今は11月、ノーベンバーである。
季節柄、牡蠣で一杯飲るのがよかろうということになった。
ノーベンバーはRのつく月であるから牡蠣を食してよいのでR。
おっと、↑これは嵐山光三郎氏の文体であった。いけない、いけない。
ともあれ、11月のある日、俺はなじみの編集者と連れだって、都内某所のオイスターバーへ繰り出したのである。
美しい女性ではなく、どちらかというとむさくるしい部類の男性編集者なんぞをなぜ誘ったかといえば、ただ飲んで食って騒ぐだけではアホらしいので、ついでに仕事の話も少しはしようと考えたからだが、これは我ながら立派な心がけであった。
しかしその日は、ひとつだけ悔いの残る出来事が生じた。
といっても仕事がらみの問題が勃発したわけではない。
飲み物に関する、ちょっとした行き違いがあったのである。
皆さんはシャブリという白ワインをご存じだろうか。
では、ギネスという黒ビールのことは知っておられるだろうか。
どちらも生牡蠣によく合う飲み物だ。
しかし我が編集者はこうのたまわったのである。
「いやあ、牡蠣にはやはり、よく冷えたシャブリですよね。それ以外は考えられません」
なにをぬかしてけつかるのであろうか。
ギネスビールの本国アイルランドでは250年も前から、牡蠣と相性のよいビールを醸造すべく、関係者一同が心を砕いてきたのである。
その結果生まれたのが、世界一牡蠣に合う黒ビールである。
決して、シャブリとかいう白ワインの向こうをはったのではない。
ギネスという黒ビールの豊かで香ばしいロースト香、クリーミーで肌理の細かい泡、ビターな味わい、そして低炭酸──これら他に類を見ない個性を具えていればこそ、ギネスは世界に冠たる黒ビールとなり得たのであり、同時に、「生牡蠣にはシャブリ」という世の常識をくつがえし得たのである。
世情に敏であるはずの編集者が、そんなことも知らずにおったのか。
俺は、そこはかとなく憮然としてしまった。
編集者のほうでもなんとなく察したらしく、
「さ、レモンでどうぞ。お好みとあらば塩も持ってきてもらいましょうか。ケチャップはどうします?」
などと小賢しく先回りして、牡蠣を小皿に取り分けてくれた。
俺はギネスをぐいぐい干しながら牡蠣を1ダース食し、編集者はシャブリをチビチビやりながら、やはり1ダースの牡蠣を食った。
まあ、それはそれでよしとしよう。
「ギネスもシャブリも、ともに世界一牡蠣に合うのである」と、俺は寛大な心持ちになりかけていた。
しかし、やつめ、「ああやっぱり牡蠣にはなんといってもシャブリだなあ」と、二度も三度も感動のため息をついたのである。
喧嘩売ってんのか?
俺がムカッときたのは言うまでもない。
俺がこんなにもうまいと思ってるギネスをばかにすんなよ、と。
だがそれを口に出すことは、さすがにはばかられる。
なんといっても、俺はもういい年をした大人の男なのだ。
大人の男がいちいち目くじら立てていたのでは格好がつかない。
とはいえ、もの言わぬは腹ふくるるわざなり。
俺の腹は牡蠣とギネスですでにふくらんでいたが、そこへさらに腹ふくるるものがのしかかってきた。
そのやるせなさといったら、いかにギネスといえども、一杯や二杯では埋め合わせがつかない。
俺は半ばやけくそになって飲み続けた。
ついでに最高級の牡蠣を追加しまくり、フライドオイスター、オイスターのオーブン焼きアンチョビバターなんかも、無理をして腹におさめてやった。
最高級のシャブリ、つまりグラン・クリュを注文させたりもした。
これは俺が飲むわけではないが、とにかく値の張るものをテーブルに並べたかったのだ。
勘定がいくらになるかなど、知ったことではない。
いやむしろ、高ければ高いほどよい。わっはっは。
という陰険な手法で俺にとっちめられた編集者は、やや悲しげな表情で会計を済ませ、店の外へ出ると、今度は急に晴れ晴れとした顔になって言った。
「これで僕は今年の接待費を全部使いきりました。いっそ気分いいです。先生、年内はもうどこにもお連れすることできませんから、どうか執筆に専念してください」
これを聞いて俺はずどんと腹をつかれる思いがした。
バルザックほどの胃袋も筆力もないくせに、なぜあんな滑稽な真似をしてしまったのか。
ごめんよ、ごめんよ、もうしないから許してくれよ、近いうちにまたどっか遊びに行こうよ、と編集者にすがりつきたかった。
しかし俺は、なんでもなさそうな顔で「じゃ」と言い残してタクシーに乗り込み、家に戻ってきた。
シャブリでもギネスでも、どっちでもええ。
どっちもうまいんやから、それでええやんか。
というのが、その日の俺の結論であった。
(つづく)