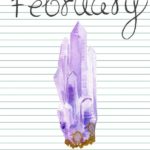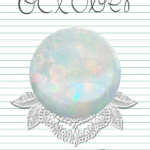●9月の別名・異称・愛称
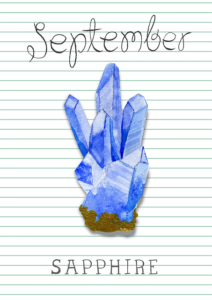
「長月(ながつき)」
9月の異称として、最もポピュラーなのは「長月」でしょう。
この一言で、秋の夜長をあらわしているのですね。
そのほか─
玄月(くろづき)
祝月(いわいづき)
詠月(ながめづき)
も9月の呼び名です。
そして季節柄、8月の異称には菊にまつわるものがいくつかあります。
菊月(きくづき)
菊開月(きくさきづき)
その昔、菊は不老長寿の霊薬とされていて、菊や月を愛でながら歌を詠むことが人々の喜びだったようです。
さらに──
竹酔月(ちくすいげつ)
寝覚月(ねざめづき)
青女月(せいじょげつ)
色取月(いろとりづき)
など、9月には洒落た異称がいろいろとあります。
紅葉月(もみじづき)
というのも素敵です。
ちょっと気が早いようですが、1ヶ月後には紅葉の季節となることから、こう呼ばれます。
そしてさらに──
晩秋(ばんしゅう)
季秋(きしゅう)
窮秋(きゅうしゅう)
残秋(ざんしゅう)
高秋(こうしゅう)
暮秋(ぼしゅう)
という呼び名もあり、移ろいゆく季節の名残が感じられます。